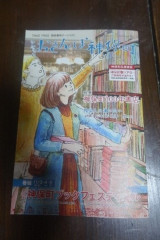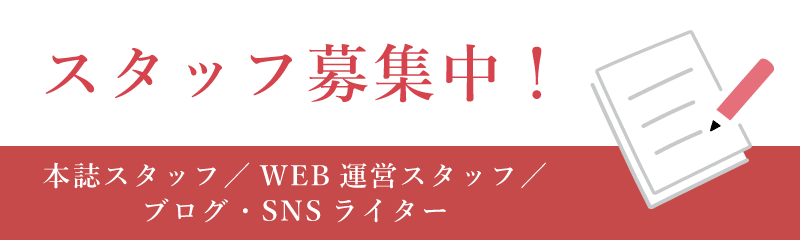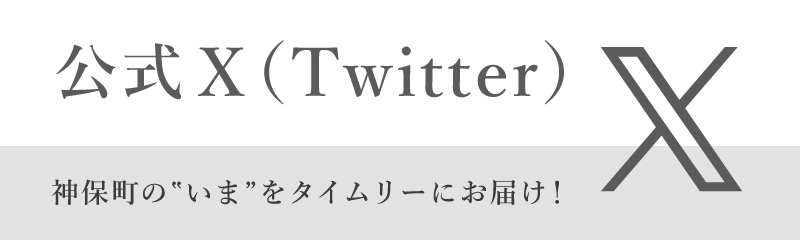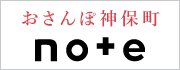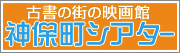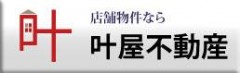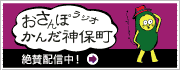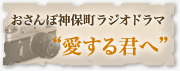2017/11/07 19:32
第27回神保町ブックフェスティバル
今年の秋は、謎解き街歩きのようなイベントは行わず、 11月3日、4日、5日の3日間神保町ブックフェスティバルのサポートをしました。 割り当てられた仕事は、こどもの本の広場の交通整理とごみの仕分け。 交通整理では、迷惑をかけてしまいましたが、3日間、大きな事故もなく終わって、ホットしました。 交通整理で、こどもの本の広場の神保町三井ビルの会場に行くと、広場はすっかり秋の彩り。 春には、桜の花が満開だった枝垂れ桜も、茶色の葉が色づいていました。 今年は、3日間、気持ちのいい秋晴れで、雨に見舞われずに、神保町ブックフェスティバルは行われ、大変よかったなと思いました。 3日間フルにボランティアに入ってしまい、神保町ブックフェスティバルのイベント等を観に行けませんでした。
それでも、1時間の休憩には、すずらん通りをぶらぶらと歩きました。 三幸園の焼きそば、揚子江菜館の肉まん、ろしあ亭のピロシキ、ティーハウスTAKANOの紅茶、神保町ボンディのチキンカレー、如水会館のクッキーなどのワゴンが並んでいました。 遅めのお昼を、3日間毎日おにぎりの小林で済ませ、おにぎりの小林のおにぎりの全種類を食べました。 おかずに三幸園のポトフ等を食べた後、本のワゴンを見て回りました。 弘文堂や有斐閣や中央経済社の専門書のワゴンを私は見て回ります。
ワゴンで本を買う楽しさは、普段お会いできない出版社の方とのやり取りできることです。 3日目の最終日、ワゴンを覗くと、 「半額の本を何冊も買うとさらに割り引きます。」というので、2冊取って渡すと、電卓をはじいて 「店長どうします。切りがよすぎる値段で値引きできませんよ。」と言ったので、 「店長お願いします。何とか勉強してください。」 と拝むように私が言えば、勉強してくれました。 店の中で、少し本を補充しようと話が聞こえたので、 「また補充されるのなら、一廻りしてからまたきます。」と言って 次の10分休みに来てみると、私の顔を覚えていて、 「すいません。コイツのせいで、補充できませんでした。」 と言い、店長は、隣の店員のせいにしていました。 最終日、すずらん通りの本部の奥に待機していると、 実行委員長が「終了時間の6時になりましたが、最後の一人のお客さんが、本を選び終わってから、3日間の神保町ブックフェスティバルは終わりにしましょう」とアナウンスしました。
それから、しばらくして、各ゴミ収集所のボランティアの人や、ワゴンの出版社さんたちが、本部に向かっていっせいにゴミを持って来ます。それを7時の業者の方が来るまで、ボランティアの学生の人と急いでまとめて仕分けていきました。
神保町ブックフェスティバルが終わた後、ボランティアの大学生と、商店街の理事の方や書店の方を囲んで、「やきとり道場」で打ち上げをやりました。 3日間、苦楽を共にした大学生とは、すっかり打ち解けて話せるようになり、就職が決まった大学生と、学年が下でこれから就職活動する大学生の方の話題を肴にお酒をのみ、盛り上がりました。
大学生のボランティアの人が卒業して社会人になっても、神保町でボランティアをしたことをいつまでも忘れないで、また、神保町ブックフェスティバルへ
神保町へ、 戻ってきてもらえれば、と思います。
島田 敏樹
2017/11/02 08:06
第58回神田古本まつり
10月27日から、神田古本まつりが始まりましたが、連日の雨・台風て、土日は中止になりました。 昨日月曜日から、晴れたので、夜行ってみました。 駿河台下の靖国通りを、ワゴンを覗きながら、歩いて行きます。 ワゴンにつるされた裸電球は昭和の家庭のお茶の間の電球を思い出させて、風情がありました。 裸電球は、駿河台下から専大通りまで並ぶワゴンの上から、本を照らします。 駿河台下の三省堂の前を通り、浮世絵の版画の飾ってある大屋書房の前を通り、レオマスカラヤの隣りは、できたばかりのラーメン屋の蘭州拉麺。
昼間はすごく行列がでしたが、夜はひっそりとしていました。 靖国通りを先に進みます。 書泉グランデと小宮山書店の間の道路を超えて、進むと 11連長屋の形が残った2連の建物がありました。 その建物の1つは本と街の案内所でした。 現在では、本と街の案内所は、すずらん通りの小学館ギャラリーの中に、移りました。 先に進むと神保町交差点に出ます。
神保町交差点の岩波ホール前には、古本まつりの赤い看板が建っていました。 看板の下のワゴンには本が並んでいます。 本は、地下鉄神保町駅の階段の前まで続いていて、漫画も並んでいます。 岩波ホールを超えると、岩波中会場。 岩波中会場の入り口の横には、毎年立っている狸の剥製、幸せ狸がいます。狸の前に御賽銭が備えてありました。
岩波中通りの赤い看板の下で、毎年、神田古本まつりの、開会式のテープカットがおこなわれます。 岩波中通の前には案内所のテントがありました。 ワゴンを観ながら、先をどんど進でいき、専大通り近くに、ミステリーのお店があります。 そこで、棚を見ると、レイモンド・チャンドラー著の「マーロウ最後の事件」という本を見つけました。 大成功した「長いお別れ」発表した後、レイモンド・チャンドラーは、最愛の妻に先立たれ、淋しさから、酒におぼれていきます。 周囲の友人のはげましにより、書き上げた「プレイバック」で、自分に言い聞かせるように、 「強くなければ生きていけない」やさしくなければ生きる意味はない。 というハードボイルドの名セリフをマーロウに言わせ、悲しみを乗り越えます。 次の「プードルスプリング物語」の執筆途中チャンドラーが亡くなり、それがマーロウ最後の事件のはずです。 「マーロウ最後の事件」は中編の最後の事件なのでしょうか。
そうこうしているうちに、店じまいの7時になり、靖国通りのワゴンの上の裸電球が次々に消えていきました。 慌てて、専大通りから神保町交差点に戻ります。 神保町交差点を渡り、「さぼうる」に入りました。 フィリップマーロウになりきって、ライムたっぷりのギブソンのダブルを飲もうと思い、注文するとない と言われたので、マティーニを飲んで帰りました。
島田 敏樹
2017/10/07 08:11
北沢書店―洋書専門古書店
靖国通りにひときわ目を引くギリシャ神殿のような大理石の建物があります。 一階は今年の5月5日にオープンした子供の本専門店ブックハウスカフェがありますが、2階は洋書専門の古書店北沢書店です。 北沢書店は、明治35年に創業し、今年で115年を向かえました。 創業から100年以上続いている書店の北沢書店に行ってみることにしました。 神保町交差点を割った手、専大通り交差点にむかった、靖国通りを進みます。 神保町交差点を少し行くと、神田古書センターがありました。
ここに昔、神保町交差点から駿河台下に向かってあった11軒長屋のような建物が建っていて、北沢書店の支店がその1つに入っていたそうです。 当時は、長屋の1つに家族と店員が一緒に暮していて、家族でお店を切り盛りしていたそうです。 その神田古書センターを通過して靖国通りを先に進むと北沢書店がありました。 北沢書店は、創業時は国文学を取り扱っていました。
昨年の古本まつりで、神保町を爆撃の危機から救ったと言われているロシアの日本学者セルゲイ・エリセーエフについての映画「ウォーナーの謎のリスト」を観に行きました。 日本の文化に興味を持ち日本に留学したセルゲイ・エリセーエフはその当時の北沢書店を訪れたそうです。 戦後再び北沢書店を訪れ、その時の写真が放映されていました。 戦後の1955年から。北沢書店は、2代目の龍太郎さんが大学助教授(英文学)だったことから、洋書の学術書の専門の書店になります。 戦後、英語教育が盛んになり、海外の書物についての関心も深まり、洋書が広く日本の大学生や研究者等に読まれるようになりました。 3代目の一郎さんの時代に北沢書店は、洋書の英文学や哲学、歴史美術などを専門の書店として、現在の建物を建てます。
本の街神保町に欧米の書店に匹敵するような立派な書店ができました。 当初は、2階は古書店の他1階は新刊書店でしたが、現在では2階の古書店のみです。 北沢書店の建物の中に入ると1階に螺旋階段があり、壁にソクラテスとプラトンの絵が飾ってありました。 2階に上がると、第一通路に、英米文学作品や小説が棚ざしされていて、シャーロックホームズ等のペーパーパックが平積みになっていました。 第二通路はシェイクスピアや演芸等、第三通路は西洋史英国史や思想等で、左端の通路は日本文化を中心とする東洋の英文の本が並んでいます。
ネットの時代になり、本はネットで買えるようになりましたが、同時に日本の文化が海外に流され、かつてのセルゲイ・エリセーエフのように日本に対して関心を持つ外国人が多く日本に訪れるようになりました。 近年、日本文化に関心を持つ外国人が、日本文化の洋書を買っていくようになったそうです。
島田 敏樹
2017/10/01 08:17
おさんぽ神保町24号配布
おさんぽ神保町24号の印刷が上がってきたので、おさんぽ神保町の設置を書店・商店中心に、お願いして回りました。 駿河台下を靖国通り沿いにスタッフの方と3人で、台車におさんぽ神保町を乗せて回ります。 、 おさんぽ神保町24号の表紙は、神保町女子のOLのコハル子さんが、外国の方と洋書の古書店の本棚で本を探しているところです。 設置のお願いに靖国通りを回っているとすごい行列ができていました。できたばかりのラーメン屋の蘭州拉麺に並んでいるのです。靖国通りを先に進みました。
おさんぽ神保町24号の特集は「神保町100年書店」です。 創業から100年経った書店と取材させて頂いたお店と、店主さんのイラストとお話しが書かれていました。 店主さんのお話しは、私も聞かせて頂きました。 明治維新後、神保町界隈にあった大名侍屋敷に、大学が建てられました。大学の学生が大学で勉強するのに欠かせない教科書・専門書を販売するため、神保町に出版社、印刷会社、書店ができてきます。 当時の印刷は活版印刷、増え続ける学生の数に追いつかず、新書をリサイクルする古書店の数が神保町に増え続けました。 靖国通りを歩いて、神保町交差点に着きます。神保町交差点を白山通りを曲り、白山通り側のすずらん通り入口を曲り、すずらん通りの商店古書店に設置をお願いして回ります。
印刷会社の印刷技術がしだいに向上し、学生に新書がいきわたるようになり、古書店が取り扱う本は、学生が勉強する専門書から、古典籍などが取り扱われるようになり、国文、美術書、洋書、等専門分野に古書店が分かれていきます。 100年の間、100年書店の書店員さんたちは時代時代に棚に並べている本を変えながら続けてこられたのだな と感じました。 ネットの時代になり、家で寝っころがっていても欲しい本が買える時代になりました。それはそれで便利ですが、 本の街神保町に行き、いろんな種類の書店を見て回り、棚に並べてある書店員さんたちのお勧めの本と出合うことも、世界が広がって行くことになります。 おさんぽ神保町24号の配布が終わり、すずらん通りの空を見上げると、綺麗な夕焼けでした。
快く設置にご協力してくださいました神保町の古書店、書店、飲食店、商店等の皆さんありがとうございました。
島田 敏樹
2017/09/12 08:22
シャーロックホームズカフェ
神田多町の早川書房1階のカフェクリスティで期間限定で営業しているシャーロックホームズカフェが9月16日までに再延長されました。 7月に日本で放映された英BBC製作のテレビドラマSHERLOCKの最新作のシーズン4と重なる時期の営業となります。 さっそく、シャーロックホームズカッフェに行ってみました。 カフェの中に入ってみると、SHERLOCKのドラマの裏話をホームズを演じたベネティクド・カンパ―バッチやワトソンを演じたマーティン・フリーマンが語っているビデオが流れていました。 店内の壁には映画やテレビドラマのホームズのポスターが貼ってあります。 席に案内され、座って、メニューを見ると、テレビドラマSHERLOCKにちなんだメニューがありました。 ワトソンの妻のメアリーという名のカクテルもあります。
フィシュ&チップスとメアリーという名のカクテルを頼みました。 ワトソンとメアリーは原作では、「四つの署名」で知り合い、ホームズがスイスのライベンバッハの滝に落ちた「最後の事件」と生還した「空き家事件」の間に、メアリーは亡くなったとされています。 テレビドラマSHERLOCKのシーズン4では、エピソード1の「6つのサッチャー」で、ワトソンの妻のメアリーが亡くなり、エピソード2の「臥せる探偵」に続いていました。 「臥せる探偵」の基となった原作の「瀕死の探偵」ではワトソンはメアリーとの結婚の2年目で、このときメアリーは亡くなっていません。
ワトソンはホームズとの共同生活を解消し、メアリーとの新居で暮らしていました。 ある日ハドスン夫人が、ワトソンの新居に訪れ「ホームズが病気で衰弱してもう1日も持たない」と呼びにきました。 ワトソンは、かつてホームズとシェアーしていたオフィス兼住居に駆けつけ、診療しようとするとホームズは「君は信頼できない」といって拒みます。 ワトソンが他の医師を紹介しても拒絶し、細菌の研究をしているスマトラに住む農園主のカルヴァートンスミスを呼んできてくれと言いました。 ワトソンはカルヴァートンスミスを呼びに行くのですが…… 原作を現代に置き換えたテレビドラマSHERLOCKでは、原作とは違った物語の展開となります。
亡くなったメアリーがワトソンに残したメセージの入ったビデオが、メアリーの死後ギクシャクしたワトソンとホームズの友情を取戻し、ホームズを救います。 フィシュ&チップスをつまみに、カクテルを飲みました。 メアリーという名のカクテルはレモンとチェリーの入った甘すっぱい味がします。 カクテルを飲んで、会計を済ませて、扉の方に行くとホームズの鹿内帽とインパネスコートがかかっていました。
「瀕死の探偵」が収録されているのは
「シャーロックホームズの最後の挨拶」アーサー・コナンドイル著 大久保 康夫訳 早川書房
島田 敏樹