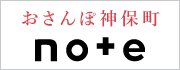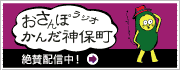2008/11/19 10:15
村上春樹『ノルウェイの森』(その2)
ご存じのとおり、『ノルウェイの森』は、記録的なベストセラー小説です(インターネットで検索してみると、87年の刊行以来の累計売り上げ部数は870万部、とあります)。このベストセラー現象に、「100パーセントの恋愛小説」という、作者自身によるコピーが大きく寄与したこともよく知られています。しかし、そう期待してこの小説を読んだ場合、読後にある釈然としない思いが残ることも否めません。それは、「100パーセントの恋愛」というのは、いったい誰と誰の関係を指していうのか、というものです。
この小説は、37歳の「僕」(作中、ワタナベ・トオルという名前が明かされます)が、20歳の頃(1970年前後)を回想する手記という体裁です。これは小説の冒頭、「僕は三十七歳で、そのときボーイング747のシートに座っていた」という一節により示されます。そして、第二章以降は(1個所の例外を除いて)まったく触れられないこの「枠組み」が、小説の設定にとって重要になります。詳しく見ていくと、「僕」がこの手記を書く背景にあるのは、37歳の「僕」が抱える、ある精神的危機です。それを回避するために、20歳の頃の記憶が呼び出され、文字に記されていくのです。その意味で、この小説のメイン・テーマは、37歳の「僕」の自己救済です。
したがって、たしかにこの小説では、20歳の頃の「僕」と直子、そして緑という女の子の間の三角関係的恋愛(??)が展開され、「僕」はいったいどっちの女の子と結ばれるんだ?、という興味を抱かせはします。しかし、この意味での恋愛(?)は、小説にとって重要なテーマではありません。
というより、この小説を大学で講義する際の(多くの)女子学生の感想からも明らかなのですが、「僕」と直子・緑の三角関係的恋愛は、結局のところ、「僕」の独り善がりや甘えにほかならず、本当の意味で恋愛といいうるものではないでしょう。では、本当の意味での恋愛とは何なのか…?? という難しい問題は、ここでは触れません(笑)。
ただ、『ノルウェイの森』でいう「100%の恋愛」とは、そんなふうに、ふつう一般的に言われるような「恋愛」ではない、とは言えるでしょう。ではそれは何なのか? というところが、『ノルウェイの森』を読み解くうえで1つのポイントになります。
さて、話を先に進めるために、簡単にあらすじを(小説内で起こる出来事の時間順に)整理しておきましょう。上述したように、この小説の中心的な話題は、「僕」の20歳の頃の出来事です。ただし、これを語るうえで欠かせないのが、その前史、とりわけ「僕」の高校時代の人間関係です。 「僕」は神戸の出身で、神戸の高校に通っていました。その頃の「僕」には、キズキという、文字通り唯一の友人がいます。このキズキの幼馴染で、(同時に)恋人だったのが直子です。「僕」の回想によれば、三人は自然に接近し、居心地の良い(三人だけの)小世界を築きます。しかし、幸福な関係は長く続きません。1967年の5月、キズキが、「ふと思いついたみたい」に自殺します。それは、まったく突然の出来事でした。それゆえ「僕」は、彼の死後、「まわりの世界の中に自分の位置をはっきり定めることができな」くなります。
翌1968年。高校を卒業した「僕」は、「神戸を離れたい」という理由だけで東京の私立大学に入学。その年の5月。中央線の電車の中で、偶然直子と再会します。キズキの死以来、1年ぶりの再会でした。直子もまた、神戸を離れ、東京で新しい生活を始めていたのです。『ノルウェイの森』に神保町が登場するのは、「僕」が直子と再会したその日の場面です。以下、第二章からその一節を引用します(引用文は単行本に拠ります。/は改行を示します)。
*
僕と直子は中央線の電車の中で偶然出会った。彼女は一人で映画でも見ようかと思って出てきたところで、僕は神田の本屋に行くところだった。べつにどちらもたいした用事があるわけではなかった。降りましょうよと直子が言って、我々は電車を降りた。それがたまたま四ツ谷駅だったというだけのことなのだ。もっとも二人きりになってしまうと我々は話しあうべき話題なんてとくに何もなかった。直子がどうして電車を降りようと言いだしたのか、僕には全然理解できなかった。話題なんてそもそもの最初からないのだ。/駅の外に出ると、彼女はどこに行くとも言わずにさっさと歩きはじめた。僕は仕方なくそのあとを追うように歩いた。直子と僕のあいだには常に一メートルほどの距離があいていた。もちろんその距離を詰めようと思えば詰めることもできたのだが、なんとなく気おくれがしてそれができなかった。僕は直子の一メートルほどうしろを、彼女の背中とまっすぐな黒い髪を見ながら歩いた。彼女は茶色の大きな髪どめをつけていて、横を向くと小さな白い耳が見えた。時々直子はうしろを振り向いて僕に話しかけた。うまく答えられることもあれば、どう答えればいいのか見当もつかないようなこともあった。何を言っているのか聞きとれないということもあった。しかし、僕に聞こえても聞こえなくてもそんなことは彼女にとってどちらでもいいみたいだった。直子は自分の言いたいことだけを言ってしまうと、また前を向いて歩きつづけた。まあいいや、散歩には良い日和だものな、と僕は思ってあきらめた。/しかし散歩というには直子の歩き方はいささか本格的すぎた。彼女は飯田橋で右に折れ、お堀ばたに出て、それから神保町の交差点を越えてお茶の水の坂を上り、そのまま本郷に抜けた。そして都電の線路に沿って駒込まで歩いた。ちょっとした道のりだ。駒込に着いたときには日はもう沈んでいた。穏かな春の夕暮だった。
*
いつものように、引用が長きにわたりました。そのわりに、神保町が登場するのはわずかです。なんだ、靖国通り沿いにただ通過しただけか(?)と思われるかもしれません。
しかし、東京をぐるっと半周するこの日の散歩は、『ノルウェイの森』における関係性のプロトタイプといえるほど重要で、その過程で、神保町、お茶の水、本郷という地名が言及されるところにもまた、この小説のテーマに関わる、重要な意味があります(以下次回)。
深津
2008/11/05 10:16
村上春樹『ノルウェイの森』(その1)
「神保町文学散歩」のコーナー。漱石に次いで取り上げる作家は村上春樹です。彼は現在、「出せば必ず売れる」数少ない作家であり、また、欧米・中国・韓国でもっとも著名な日本文学者の一人です。
まずは作家のプロフィールを確認しておきましょう。村上春樹は1949(昭24)年、京都生まれ。いわゆる「全共闘世代」です(あとで述べますが、この時の体験が、彼の小説に大きな影を落とすことになります)。県立神戸高校卒業後、早稲田大学第一文学部で演劇学を専修。大学在学中(留年中?)に陽子夫人と結婚し、ジャズ喫茶を経営。1979(昭54)年、デビュー作『風の歌を聴け』で「群像新人文学賞」受賞。1987(昭62)年、『ノルウェイの森』が空前のベストセラーとなり、以降、『ねじまき鳥クロニクル』、『海辺のカフカ』といった大作を発表しています。このなかには、読んだことがある(買った覚えがある)という作品も多いのではないでしょうか。
さて、その村上春樹と神保町界隈との接点ですが、これが意外に(?)ありません。彼の小説の舞台といえば、やはり定番は、かつて彼がジャズ喫茶を経営していた青山(神宮外苑)界隈ということになります。小田急線沿線や中央線沿線というのもよく出てきます。いずれもいわゆる「山の手」です。
これに対して、東京の「下町」側は、とくに彼の初期作品にはほとんど出てきません。村上春樹の小説に、(上野・神田・日本橋といった)「下町」側が頻出するようになるのは、『ノルウェイの森』が最初です。今回「神保町文学散歩」として取り上げるのも、この『ノルウェイの森』に描かれた神保町です。(以下次回)
(↑)赤&緑と「クリスマス・カラー」のブックカバー。実際、20年前には、(恋人同士の)クリスマス・プレゼントとして人気でした。懐かしい…。
深津