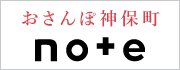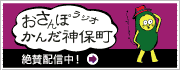2008/10/26 10:17
夏目漱石『門』(その5)
今日で『門』の最終回です。
駿河台下の繁華街を散歩する宗助は、西洋小間物屋で売られる襟飾り(ネクタイ)や、呉服店の出店で見た女の半襟に食指を動かしかけます。しかし結局それらは買わず、「達磨の恰好」をした「大きなゴム風船」だけ買って帰ります。中国禅宗の開祖が座禅した姿にちなむこの人形の姿が、のちの宗助の参禅を予告するわけですが、なぜかそれに惹かれてしまうところに、いまの宗助の無意識があらわれています。彼は、達磨の尻のすわったところに感心しています。これは逆に言えば、今の彼自身の尻がすわっていない(安定していない)ということを暗示します(付け加えれば、宗助と同年輩の達磨売りの超然とした姿は、宗助の別の生のあり方を示唆します)。
そのことに、まだこの時点の宗助は、はっきりと気づいていません。その証拠に、再び電車に乗り、郊外の終点に着いた宗助は、こんなことを思いながら自宅まで歩きます。
*
今日の日曜も、のんびりしたお天気も、もうすでにおしまいだと思うと、少しはかないようなまた淋しいような一種の気分が起こってきた。そうして明日からまた例によって例のごとく、せっせと働かなくてはならないからだと考えると、今日半日の生活が急に惜しくなって、残る六日半の非精神的な行動が、いかにもつまらなく感ぜられた。歩いているうちにも、日当たりの悪い、窓の乏しい、大きな部屋の模様や、隣にすわっている同僚の顔や、野中さんちょっとという上官の様子ばかり目に浮かんだ。(二)
*
ここで重要なのは、「例によって例のごとく」という言葉です。この言葉が端的に表しているように、宗助はサラリーマンとしてのルーチン(の連続)を、まだ疑っていないのです。
次に駿河台下が登場するのは、五章です。食事の際、どうした拍子か宗助の歯が痛み出し、さわってみるとぐらぐらする。そこで宗助は、土曜日の午後、役所の帰りに歯科医に立ち寄ります。小説本文には、「彼はその日役所の帰りがけに駿河台下まで来て、電車をおりて、酸いものをほおばったような口をすぼめて一、二町歩いた後、ある歯医者の門をくぐったのである」(五)とあります((その1)でaimさんにコメント頂いたように、漱石が駿河台の井上眼科に通っていたのは有名ですが、この歯科医が実在のものがどうかはわかりません。ご存知の方はご教示ください)。
そこで宗助は、歯科医から、次のような宣告を受けます。(宗助の歯の根もとが)こうゆるむと、もう、もとのようにしまる(治る)わけにはいかない。なにしろ中がまるで腐っているから。もっとひどければ抜いてしまうが、まだそれほどでもないので、今は痛みだけを止めておくようにする、と。
ここで歯科医(漱石)は、宗助の歯の様子を語りながら、「もう一つの意味」を語っています。それは、宗助の今の生のありようについてです。すなわち、罪を負った宗助の生活は、もう以前のように戻らない。ただ、今の時点ではまだ、決定的な破局が迫っているわけではないので、全てを御破算にする必要はない。根本的な治療というより(それを先延ばしにして)、罪の痛みを麻痺させるような処置で間に合うだろう、と。
結論から先に言えば、これは『門』全体のストーリーの予告でもあります。あらすじに記したように、『門』における破局の危機は、安井が崖上の坂井の家に現れる場面に集約されます。安井の出現を知らされた宗助は、このことを妻のお米にも告げられず苦悶します。しかし、結局この決定的な破局は回避されます。魂の救済を求めたこの後の宗助の参禅も失敗し、罪の痛みが鈍化し麻痺していくような、日々の継続が示唆されて終わるわけです。
ただし、宗助に進歩(成長)がないわけではありません。秋口の日曜日からはじまったこの小説は、冬に向かうにつれ徐々に危機(の予兆)を深めていき、正月早々の安井訪問でそのクライマックスを迎えたあと、梅が咲き、春が感じられるようになった日曜日に終わります。決定的な危機(破局)を回避したあとの、何かほっとするような終わり方、とも受け取れます。じっさい、小説の最後でお米が、ようやく春が来てよかった、ということを言っています。けれども、これに対し宗助は、「うん、しかしまたじきに冬になるよ」(二十三)と返答するのです。つまり、今回は危機をやり過ごせたが、それは小康を保ているにすぎない…。これは宗助が、歯科医でうけた宣告の「もうひとつの意味」を理解した、とは言わないまでも、感じたような結末になっています。
では、どこで宗助はそれを「感じた」のでしょうか。根がすっかり腐ってしまった歯が、じつは彼の生活そのもの(の象徴)でもあった、という事実を宗助がはっきり悟るのは、例の、安井が出現するという晩です。役所からの帰り、(隣家に安井が訪れる)自宅にまっすぐ帰る気になれない宗助は、駿河台下で自宅へ向かう電車に乗り換えず、近くの牛肉店へ立ち寄って酒を飲み、それからさらに、(電車に乗らず)歩いて家まで帰ります。その途中、寒くて暗い冬の夜道で、彼は、「根の締まらない人間として、かく漂浪の雛形を演じつつある自分の心を省み」ます(十七)。つまりここでも、(歯科医訪問の場合と同様)単なる乗り換え駅というルーチンから外れた(時の)駿河台下が、重要な役割を果たしているのです。
以上、『門』に描かれた駿河台下界隈を紹介してきました。
面白いのは、駿河台下という場所が、宗助のルーチン(通勤経路)を構成するものでありながら、彼がそこから逸れたとき、ルーチン(宗助の日常の反復)の脆弱さを顕在化させてしてしまうという、場所の両義性です。すでに指摘したランプのように、『門』という小説では、こうした両義的なアイテムが重要なのですが、当時有数の繁華街であり、また自身にもゆかりの深い街を、漱石はこのようなかたちで描き出しました。ちなみに、『門』のあと執筆された『彼岸過迄』(1912(明45)年)という小説では、小川町界隈が重要な場所として描かれています。
季節はいよいよ読書の秋。これをきっかけに、漱石の小説を読みなおして頂ければうれしいです。
次回は、村上春樹の小説に描かれた神保町界隈を紹介します。
深津
2008/10/19 10:18
夏目漱石『門』(その4)
前回は、宗助が日曜日の駿河台下界隈を散歩する場面を引用しました。洋書屋や雑誌屋、時計屋、西洋小間物を売る店から京都の老舗呉服店(モデルは「ゑり善」)の出店まで、お店のバラエティは今日以上かもしれません。くわえて、路上の(実演?)販売も行われているようで、当時のこの界隈の賑わいの様子が窺えます。
引用した場面で宗助が歩いているのは、駿河台下から小川町にかけての、今日でいう靖国通り沿いという想定でしょうか。前回ふれたように、この通りは当時(明治末期)、銀座通りにも匹敵する有数の繁華街でした。ただし、電車を降りて右側の洋書屋を覗き、「せわしい通り」を渡った宗助が、再び右側の店のウインドウ・ショッピングを続けるとすると、彼が歩いているのは今の「すずらん通り」である、という「見立て」も可能性です。
馬場孤蝶という文学者の回想録(『明治の東京』中央公論社、1942(昭17)年)によれば、駿河台下から俎橋へ抜ける大通り(靖国通り)は、電車開通にあわせて広げられたいわば「新道」で、「本道」(?)は元来、「すずらん通り」だったそうです。当然、当時はこちらのほうが賑わっていました。
写真は、宗助が電車を降りた駿河台下の現在の様子です。手前の大通りが靖国通り、真ん中の狭い(?)通りが「すずらん通り」です。

下の写真は、小川町方面から駿河台下を望んだところ。現在ではスポーツ用品店が立ち並んでいます。

ところで、『門』という小説の中で、駿河台下という場所には大きく分けて二つの意味があります。
『門』の駿河台下は、まず、宗助の日常のルーチン(繰り返される決まり事)を構成するもののひとつです。二章にこんな記述があります。
*
彼は年来東京の空気を吸って生きている男であるのみならず、毎日役所の行き通いには電車を利用して、にぎやかな町を二度ずつはきっと行ったり来たりする習慣になっているのではあるが、からだと頭に楽がないので、いつでもうわの空で素通りをすることになっているから、自分がそのにぎやかな町の中に活きているという自覚は近来とんと起こったことがない。
*
つまり宗助が、自宅と役所を往復する毎日に埋没するかぎりにおいて、――言い換えれば、サラリーマン(小市民)としての変化に乏しい日常のルーチンを反復するかぎりにおいて、駿河台下は「うわの空で素通りをする」、たんなる乗り換え駅に過ぎません。日常のルーチンの構成要素でありながら、とくに(は)意識されない場所なのです。
宗助は、こうした日常のルーチンに倦みながら、しかしいっぽうで、それが侵されることを恐れています。彼には、恐れるだけの根拠(過去の罪意識)があったからです。これまでも見てきてように、『門』という小説は、「崖下(の家)」や、「ランプの影」のイメージなどで、平穏そうに見える宗助夫婦の日常がじつは脆弱であることを仄めかしていました。
『門』の駿河台下は、(いま述べたように)宗助の日常のルーチンの構成要素で(も)あるのですが、ところが彼がそこから逸脱したときには、つまり、電車の乗り換え駅という以外(以上)の意味でこの場所が言及されるときには、一転して、宗助の日常がじつは脆弱であることを彼に突きつける(自覚させる)場所に変貌します。
前回引用した場面の後半で、宗助が「達磨の恰好」をした「大きなゴム風船」を買う理由もこれに関わります。(以下次回)
深津
2008/10/10 10:20
夏目漱石『門』(その3)
前回、宗助夫婦の「日常のリアリティー」を構築するのに、東京の都市空間が巧みに利用されていると書きました。『都市空間のなかの文学』(ちくま学芸文庫)という本のなかで前田愛さんが注目されているのですが、たとえば、宗助夫婦の住まいは、電車(市電)の終点から徒歩で20分ほど奥まったこんなところにあります。(なお、以下、本文の引用はすべて角川文庫版によります。)
*
魚勝という肴屋の前を通り越して、その五、六軒先の路地とも横丁ともつかない所を曲ると、行き当りが高い崖で、その左右に四、五軒同じ構えの貸家が並んでいる。ついこの間まではまばらな杉垣の奥に、御家人でも住み古したと思われる、ものさびた家も一つ地所のうちに混じっていたが、崖の上の坂井という人がここを買ってから、たちまち萱葺をこわして、杉垣を引き抜いて、今のような新らしい普請に建てかえてしまった。宗助の家は横丁を突き当って、いちばん奥の左側で、すぐの崖下だから、多少陰気ではあるが、その代り通りからはもっとも隔たっているだけに、まあいくぶんか閑静だろうというので、細君と相談のうえ、とくにそこを選んだのである。(二)
*
いまでいう郊外の、安普請の新興住宅地といった趣でしょうか。庶民向けの新開地ですから、インフラも十分ではありません。「崖の上の坂井(の家)」には引かれている電気も、崖下の宗助の家には引かれていません。それで夜になると、宗助の家ではランプを灯します。漱石はこれを巧みに用いて、宗助夫婦のありようを次のように描きだします。
*
やがて日が暮れた。昼間からあまり車の音を聞かない町内は、宵の口からしんとしていた。夫婦は例の通りランプのもとに寄った。広い世の中で、自分たちのすわっているところだけが明るく思われた。そうしてこの明るい灯影に、宗助はお米だけを、お米はまた宗助だけを意識して、ランプの力の届かない暗い社会は忘れていた。彼らは毎晩こう暮らしてゆくうちに、自分たちの生命を見出していたのである。(五)
*
ランプの灯だから、光が部屋の隅々まで届きません。ランプの灯で(逆に)際立たされる陰の存在が、夫婦のいまを脅かす過去の罪を暗示する。これが部屋を明るく照らす電灯だったらそうはいかないわけで、こんなところ――ひっそりした郊外の新開地に夫婦の住まいを設定したところにも、漱石の周到な計算が窺えます。
ところで、宗助はいっぽうで、日本の中心・丸の内の役所に勤める下級官吏(サラリーマン)という設定でした。日曜を除く毎朝(毎夕)、彼は郊外(丸の内)から丸の内(郊外)まで電車(市電)で通勤しています。その乗り換え駅が、駿河台下なのです。いまの駿河台下交差点あたりは、1909年当時、お茶の水から坂を下って錦町方面へ抜ける路線と、九段下から小川町方面へ通じる路線が交差する交通の要衝で、銀座通りに匹敵する市内有数の繁華街だったそうです。
『門』の二章には、駿河台下の当時の賑わいが次のように描写されています。これは宗助の通勤場面ではなく、彼が気分転換で訪れる日曜日の昼下がりの場面です。いまから100年まえの街の様子を知るうえで興味深いものなので、少し長いですが引用します。
*
宗助は駿河台下で電車を降りた。降りるとすぐ右側の窓ガラスの中に美しく並べてある洋書に眼がついた。宗助はしばらくその前に立って、赤や青や縞や模様の上に、あざやかにたたき込んである金文字を眺めた。表題の意味はむろんわかるが、手に取って、中をしらべてみようという好奇心はちっとも起らなかった。本屋の前を通ると、きっと中へはいって見たくなったり、中へはいると必ずなにか欲しくなったりするのは、宗助から云うと、すでに一昔まえの生活である。ただ History of Gambling(博奕史)と云うのが、ことさらに美装して、一番まん中に飾られてあったので、それがいくぶんか彼の頭にとっぴな新し味を加えただけであった。
宗助は微笑しながら、せわしい通りを向こう側へ渡って、今度は時計屋の店をのぞき込んだ。(中略)蝙蝠傘屋の前にもちょっと立ちどまった。西洋小間物を売る店先では、シルクハットの傍にかけてあった襟飾りに眼がついた。(中略)呉服店でもだいぶ立見をした。鶉御召だの、高貴織だの、清凌織だの、自分の今日まで知らずに過ぎた名をたくさん覚えた。京都の襟新という家の出店の前で、窓ガラスへ帽子のつばを突きつけるように近く寄せて、精巧に刺繍をした女の半襟を、いつまでも眺めていた。そのうちにちょうど細君に似合いそうな上品なのがあった。買っていってやろうかという気がちょっと起るや否や、そりゃ五、六年前のことだという考えが後から出てきて、せっかく心持ちのいい思いつきをすぐもみ消してしまった。宗助は苦笑しながら窓ガラスを離れてまた歩き出したが、それから半町ほどの間はなんだかつまらないような気分がして、往来にも店先にも格段の注意を払わなかった。
ふと気がついてみると角に大きな雑誌屋があって、その軒先には新刊の書物が大きな字で広告してある。梯子のような細長い枠へ紙を張ったり、ペンキ塗りの一枚板へ模様画みたような色彩を施こしたりしてある。宗助はそれをいちいち読んだ。著者の名前も作物の名前も、一度は新聞の広告で見たようでもあり、またまったく新奇のようでもあった。
この店の曲り角の影になった所で、黒い山高帽をかぶった三十ぐらいの男が地面の上へ気楽そうにあぐらをかいて、ええお子供衆のお慰みと言いながら、大きなゴム風船をふくらましている。それがふくれると自然と達磨の恰好になって、いいかげんなところに目口まで墨で書いてあるのに宗助は感心した。そのうえ一度息を入れると、いつまでもふくれている。かつ指の先へでも、手の平の上へでも自由に尻がすわる。それが尻の穴へようじのような細いものを突っ込むと、しゅうっと一度に収縮してしまう。
忙がしい往来の人は何人でも通るが、だれも立ちどまって見るほどのものはない。山高帽の男は賑やかな町の隅に、冷やかにあぐらをかいて、身の周囲に何事が起りつつあるかを感ぜざるもののごとくに、ええお子供衆のお慰みと言っては、達磨をふくらましている。宗助は一銭五厘出して、その風船を一つ買って、しゅっと縮ましてもらって、それを袂へ入れた。きれいな床屋へ行って、髪を刈りたくなったが、どこにそんなきれいなのがあるか、ちょっと見つからないうちに、日がかぎって来たので、また電車へ乗って、宅の方へ向った。
*
次回はこの部分を読み解きながら、『門』という小説が、駿河台下という場所にどのような意味を持たせているのか考察してみます。
深津
2008/10/03 10:21
夏目漱石『門』(その2)
『門』は1910(明43)年3月から6月まで東京朝日新聞に連載されました。写真は角川文庫版のブックカバーです(「わたせせいぞう」のイラストが懐かしいですね)。

こんなあらすじの小説です(注・あえて最後まで書きませんが、ストーリー上の重要な伏線(後で述べる事柄を前もってほのめかしておくこと)のいくつかを明かしています。ネタバレに注意してください)。
小説内の現在時は1909年の秋から翌年春にかけて。主人公の野中宗助とその妻・米(御米)は、傍からみると仲睦まじい夫婦に見え、また実際そうなのですが、しかし二人の生活には時折暗い影が差しこみます。あとで明らかになるように、宗助には、親友だった安井の内縁の妻(これが御米です)を奪ってしまった過去(御米の側からすれば、内縁の夫(安井)を裏切った過去)があり、二人それぞれの仕方で、今もその罪意識に脅かされているのです。
そんな彼らが、今のところは小康を保っていても、いつ崩れるか分らない「崖の下」の家にひっそり暮らしている……という設定は象徴的で、事実小説の終盤で、宗助に最大の危機が訪れます。親友と内縁の妻に裏切られ、中国大陸に渡った安井が、宗助の「崖の上」の隣家を訪れるというのです。このことを御米にも打ち明けられず、一人苦しむ宗助は、とうとう、救いを求めて鎌倉の禅寺に赴きます。はたして、宗助は救われるのでしょうか……。
*
ご存知の方も多いと思いますが、漱石は最初から小説家だったわけではありません。東大などで教鞭をとる、将来を嘱望された学者(英文学)でした。『吾輩は猫である』(1904年)などは、本業の傍ら余技として書かれたものです。でもこれが評判になって、請われるまま小説を書き継いでいるうちに、朝日新聞社からスカウトされます(当時、連載小説は新聞の売り上げを左右する重要なコンテンツでした)。漱石自身、教職に嫌気がさしていたのかもしれません。1907年、「職業作家」として朝日新聞に入社します。
以来、漱石は『虞美人草』(1907年)、『三四郎』(1908年)、『それから』(1909年)……と長編連載を続けます。連載ですから小説はこま切れです。だからといって、読者を飽きさせてはいけません。少なくとも、「続きはどうなるんだろう?」という期待を抱かせる必要があるわけで、そんなところから、予告や伏線など、漱石の小説には読者を飽きさせない工夫が張り巡らされています(小説を読むときには、その発表形態も念頭において読むとよいでしょう)。
さて、話を『門』に戻します。
『門』という題名は、新聞に予告を出す必要上、漱石の弟子が(勝手に?)付けました。前作『それから』で、自然の法に遵い、友人の妻を奪った結果、社会から追放された主人公の行く先は宗教しかない、と考えたからかもしれません(余談ですが、『それから』という題名の由来も、前作『三四郎』の「それから」が書かれているから『それから』だ、といういい加減(?)なものです)。
むろん漱石自身も、『それから』の発展として宗教による救済の可能性を意識していたようで、それは何よりも主人公の名前・「宗助」にあらわれていますし、あらすじで紹介したように、最後のほうで宗助に参禅させます。
しかし『門』という小説の魅力は、そうした「頭でっかちなテーマ」よりも、むしろ幸福そうに自足しながら、でもどこか陰のあるサラリーマン夫婦の日常を、秋から冬、冬から春という季節の移り変わりにシンクロさせながら淡々と描き出した、その筆致にあるといえます。
そして、そうした「日常のリアリティー」を構築するうえで、漱石は東京という都市空間を巧みに利用しています。次回は、いよいよ、『門』に描かれた神保町界隈の紹介です。
深津
2008/10/01 10:22
夏目漱石『門』(その1)
本の街・神保町は、文学にゆかりの深い街です。
このブログでは、小説中に描かれた神保町界隈を、昔と今を対照しながら紹介していきます。それと同時に、作品のみどころ(読みどころ?)や作家紹介など、読書案内的なこともしていくつもりです。
もっとも、ライター自身、泥縄の手探り状態……。こま切れ更新必至ですが、よろしくお付き合いください。
さて、記念すべき第1回。最初にとりあげるのは、やはり、誰もが知っている千円札の人・夏目漱石です。
猿楽町のお茶の水小学校(旧・錦華小学校)に、「吾輩は猫である。名前はまだ無い。 明治十一年 夏目漱石 錦華に学ぶ」という碑がたっていまね(写真)。

ほかにも、駿河台にあった成立学舎という予備校に通ったり、明治大学で教鞭をとったりするなど、漱石とこの界隈の関わりは深いものがあり、そんなことも影響してか、坊っちゃんの下宿先が小川町だったり(『坊っちゃん』、先生の散歩コースに「猿楽街から神保町の通り」が出てきたり(『こころ』)、注意深く読んでみると、漱石の小説にはお馴染みの地名が散見されます。
そんななかで、ここで読んでみたいのは、『門』(1910(明43)年)という小説に描かれた神保町界隈です。
この小説は、漱石のなかでは比較的地味な部類にはいる小説ですが、最近、『崖の上のポニョ』の宗介が、この小説の主人公・「崖の下の」宗助にちなんでいる、ということで(ちょっとだけ?)話題になりました。次回は、『門』のあらすじと読みどころを紹介します。
深津