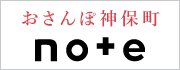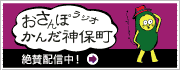2008/10/26 10:17
夏目漱石『門』(その5)
今日で『門』の最終回です。
駿河台下の繁華街を散歩する宗助は、西洋小間物屋で売られる襟飾り(ネクタイ)や、呉服店の出店で見た女の半襟に食指を動かしかけます。しかし結局それらは買わず、「達磨の恰好」をした「大きなゴム風船」だけ買って帰ります。中国禅宗の開祖が座禅した姿にちなむこの人形の姿が、のちの宗助の参禅を予告するわけですが、なぜかそれに惹かれてしまうところに、いまの宗助の無意識があらわれています。彼は、達磨の尻のすわったところに感心しています。これは逆に言えば、今の彼自身の尻がすわっていない(安定していない)ということを暗示します(付け加えれば、宗助と同年輩の達磨売りの超然とした姿は、宗助の別の生のあり方を示唆します)。
そのことに、まだこの時点の宗助は、はっきりと気づいていません。その証拠に、再び電車に乗り、郊外の終点に着いた宗助は、こんなことを思いながら自宅まで歩きます。
*
今日の日曜も、のんびりしたお天気も、もうすでにおしまいだと思うと、少しはかないようなまた淋しいような一種の気分が起こってきた。そうして明日からまた例によって例のごとく、せっせと働かなくてはならないからだと考えると、今日半日の生活が急に惜しくなって、残る六日半の非精神的な行動が、いかにもつまらなく感ぜられた。歩いているうちにも、日当たりの悪い、窓の乏しい、大きな部屋の模様や、隣にすわっている同僚の顔や、野中さんちょっとという上官の様子ばかり目に浮かんだ。(二)
*
ここで重要なのは、「例によって例のごとく」という言葉です。この言葉が端的に表しているように、宗助はサラリーマンとしてのルーチン(の連続)を、まだ疑っていないのです。
次に駿河台下が登場するのは、五章です。食事の際、どうした拍子か宗助の歯が痛み出し、さわってみるとぐらぐらする。そこで宗助は、土曜日の午後、役所の帰りに歯科医に立ち寄ります。小説本文には、「彼はその日役所の帰りがけに駿河台下まで来て、電車をおりて、酸いものをほおばったような口をすぼめて一、二町歩いた後、ある歯医者の門をくぐったのである」(五)とあります((その1)でaimさんにコメント頂いたように、漱石が駿河台の井上眼科に通っていたのは有名ですが、この歯科医が実在のものがどうかはわかりません。ご存知の方はご教示ください)。
そこで宗助は、歯科医から、次のような宣告を受けます。(宗助の歯の根もとが)こうゆるむと、もう、もとのようにしまる(治る)わけにはいかない。なにしろ中がまるで腐っているから。もっとひどければ抜いてしまうが、まだそれほどでもないので、今は痛みだけを止めておくようにする、と。
ここで歯科医(漱石)は、宗助の歯の様子を語りながら、「もう一つの意味」を語っています。それは、宗助の今の生のありようについてです。すなわち、罪を負った宗助の生活は、もう以前のように戻らない。ただ、今の時点ではまだ、決定的な破局が迫っているわけではないので、全てを御破算にする必要はない。根本的な治療というより(それを先延ばしにして)、罪の痛みを麻痺させるような処置で間に合うだろう、と。
結論から先に言えば、これは『門』全体のストーリーの予告でもあります。あらすじに記したように、『門』における破局の危機は、安井が崖上の坂井の家に現れる場面に集約されます。安井の出現を知らされた宗助は、このことを妻のお米にも告げられず苦悶します。しかし、結局この決定的な破局は回避されます。魂の救済を求めたこの後の宗助の参禅も失敗し、罪の痛みが鈍化し麻痺していくような、日々の継続が示唆されて終わるわけです。
ただし、宗助に進歩(成長)がないわけではありません。秋口の日曜日からはじまったこの小説は、冬に向かうにつれ徐々に危機(の予兆)を深めていき、正月早々の安井訪問でそのクライマックスを迎えたあと、梅が咲き、春が感じられるようになった日曜日に終わります。決定的な危機(破局)を回避したあとの、何かほっとするような終わり方、とも受け取れます。じっさい、小説の最後でお米が、ようやく春が来てよかった、ということを言っています。けれども、これに対し宗助は、「うん、しかしまたじきに冬になるよ」(二十三)と返答するのです。つまり、今回は危機をやり過ごせたが、それは小康を保ているにすぎない…。これは宗助が、歯科医でうけた宣告の「もうひとつの意味」を理解した、とは言わないまでも、感じたような結末になっています。
では、どこで宗助はそれを「感じた」のでしょうか。根がすっかり腐ってしまった歯が、じつは彼の生活そのもの(の象徴)でもあった、という事実を宗助がはっきり悟るのは、例の、安井が出現するという晩です。役所からの帰り、(隣家に安井が訪れる)自宅にまっすぐ帰る気になれない宗助は、駿河台下で自宅へ向かう電車に乗り換えず、近くの牛肉店へ立ち寄って酒を飲み、それからさらに、(電車に乗らず)歩いて家まで帰ります。その途中、寒くて暗い冬の夜道で、彼は、「根の締まらない人間として、かく漂浪の雛形を演じつつある自分の心を省み」ます(十七)。つまりここでも、(歯科医訪問の場合と同様)単なる乗り換え駅というルーチンから外れた(時の)駿河台下が、重要な役割を果たしているのです。
以上、『門』に描かれた駿河台下界隈を紹介してきました。
面白いのは、駿河台下という場所が、宗助のルーチン(通勤経路)を構成するものでありながら、彼がそこから逸れたとき、ルーチン(宗助の日常の反復)の脆弱さを顕在化させてしてしまうという、場所の両義性です。すでに指摘したランプのように、『門』という小説では、こうした両義的なアイテムが重要なのですが、当時有数の繁華街であり、また自身にもゆかりの深い街を、漱石はこのようなかたちで描き出しました。ちなみに、『門』のあと執筆された『彼岸過迄』(1912(明45)年)という小説では、小川町界隈が重要な場所として描かれています。
季節はいよいよ読書の秋。これをきっかけに、漱石の小説を読みなおして頂ければうれしいです。
次回は、村上春樹の小説に描かれた神保町界隈を紹介します。
深津