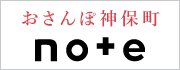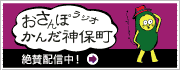2008/10/19 10:18
夏目漱石『門』(その4)
前回は、宗助が日曜日の駿河台下界隈を散歩する場面を引用しました。洋書屋や雑誌屋、時計屋、西洋小間物を売る店から京都の老舗呉服店(モデルは「ゑり善」)の出店まで、お店のバラエティは今日以上かもしれません。くわえて、路上の(実演?)販売も行われているようで、当時のこの界隈の賑わいの様子が窺えます。
引用した場面で宗助が歩いているのは、駿河台下から小川町にかけての、今日でいう靖国通り沿いという想定でしょうか。前回ふれたように、この通りは当時(明治末期)、銀座通りにも匹敵する有数の繁華街でした。ただし、電車を降りて右側の洋書屋を覗き、「せわしい通り」を渡った宗助が、再び右側の店のウインドウ・ショッピングを続けるとすると、彼が歩いているのは今の「すずらん通り」である、という「見立て」も可能性です。
馬場孤蝶という文学者の回想録(『明治の東京』中央公論社、1942(昭17)年)によれば、駿河台下から俎橋へ抜ける大通り(靖国通り)は、電車開通にあわせて広げられたいわば「新道」で、「本道」(?)は元来、「すずらん通り」だったそうです。当然、当時はこちらのほうが賑わっていました。
写真は、宗助が電車を降りた駿河台下の現在の様子です。手前の大通りが靖国通り、真ん中の狭い(?)通りが「すずらん通り」です。

下の写真は、小川町方面から駿河台下を望んだところ。現在ではスポーツ用品店が立ち並んでいます。

ところで、『門』という小説の中で、駿河台下という場所には大きく分けて二つの意味があります。
『門』の駿河台下は、まず、宗助の日常のルーチン(繰り返される決まり事)を構成するもののひとつです。二章にこんな記述があります。
*
彼は年来東京の空気を吸って生きている男であるのみならず、毎日役所の行き通いには電車を利用して、にぎやかな町を二度ずつはきっと行ったり来たりする習慣になっているのではあるが、からだと頭に楽がないので、いつでもうわの空で素通りをすることになっているから、自分がそのにぎやかな町の中に活きているという自覚は近来とんと起こったことがない。
*
つまり宗助が、自宅と役所を往復する毎日に埋没するかぎりにおいて、――言い換えれば、サラリーマン(小市民)としての変化に乏しい日常のルーチンを反復するかぎりにおいて、駿河台下は「うわの空で素通りをする」、たんなる乗り換え駅に過ぎません。日常のルーチンの構成要素でありながら、とくに(は)意識されない場所なのです。
宗助は、こうした日常のルーチンに倦みながら、しかしいっぽうで、それが侵されることを恐れています。彼には、恐れるだけの根拠(過去の罪意識)があったからです。これまでも見てきてように、『門』という小説は、「崖下(の家)」や、「ランプの影」のイメージなどで、平穏そうに見える宗助夫婦の日常がじつは脆弱であることを仄めかしていました。
『門』の駿河台下は、(いま述べたように)宗助の日常のルーチンの構成要素で(も)あるのですが、ところが彼がそこから逸脱したときには、つまり、電車の乗り換え駅という以外(以上)の意味でこの場所が言及されるときには、一転して、宗助の日常がじつは脆弱であることを彼に突きつける(自覚させる)場所に変貌します。
前回引用した場面の後半で、宗助が「達磨の恰好」をした「大きなゴム風船」を買う理由もこれに関わります。(以下次回)
深津