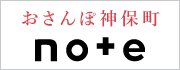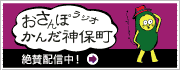2008/10/03 10:21
夏目漱石『門』(その2)
『門』は1910(明43)年3月から6月まで東京朝日新聞に連載されました。写真は角川文庫版のブックカバーです(「わたせせいぞう」のイラストが懐かしいですね)。

こんなあらすじの小説です(注・あえて最後まで書きませんが、ストーリー上の重要な伏線(後で述べる事柄を前もってほのめかしておくこと)のいくつかを明かしています。ネタバレに注意してください)。
小説内の現在時は1909年の秋から翌年春にかけて。主人公の野中宗助とその妻・米(御米)は、傍からみると仲睦まじい夫婦に見え、また実際そうなのですが、しかし二人の生活には時折暗い影が差しこみます。あとで明らかになるように、宗助には、親友だった安井の内縁の妻(これが御米です)を奪ってしまった過去(御米の側からすれば、内縁の夫(安井)を裏切った過去)があり、二人それぞれの仕方で、今もその罪意識に脅かされているのです。
そんな彼らが、今のところは小康を保っていても、いつ崩れるか分らない「崖の下」の家にひっそり暮らしている……という設定は象徴的で、事実小説の終盤で、宗助に最大の危機が訪れます。親友と内縁の妻に裏切られ、中国大陸に渡った安井が、宗助の「崖の上」の隣家を訪れるというのです。このことを御米にも打ち明けられず、一人苦しむ宗助は、とうとう、救いを求めて鎌倉の禅寺に赴きます。はたして、宗助は救われるのでしょうか……。
*
ご存知の方も多いと思いますが、漱石は最初から小説家だったわけではありません。東大などで教鞭をとる、将来を嘱望された学者(英文学)でした。『吾輩は猫である』(1904年)などは、本業の傍ら余技として書かれたものです。でもこれが評判になって、請われるまま小説を書き継いでいるうちに、朝日新聞社からスカウトされます(当時、連載小説は新聞の売り上げを左右する重要なコンテンツでした)。漱石自身、教職に嫌気がさしていたのかもしれません。1907年、「職業作家」として朝日新聞に入社します。
以来、漱石は『虞美人草』(1907年)、『三四郎』(1908年)、『それから』(1909年)……と長編連載を続けます。連載ですから小説はこま切れです。だからといって、読者を飽きさせてはいけません。少なくとも、「続きはどうなるんだろう?」という期待を抱かせる必要があるわけで、そんなところから、予告や伏線など、漱石の小説には読者を飽きさせない工夫が張り巡らされています(小説を読むときには、その発表形態も念頭において読むとよいでしょう)。
さて、話を『門』に戻します。
『門』という題名は、新聞に予告を出す必要上、漱石の弟子が(勝手に?)付けました。前作『それから』で、自然の法に遵い、友人の妻を奪った結果、社会から追放された主人公の行く先は宗教しかない、と考えたからかもしれません(余談ですが、『それから』という題名の由来も、前作『三四郎』の「それから」が書かれているから『それから』だ、といういい加減(?)なものです)。
むろん漱石自身も、『それから』の発展として宗教による救済の可能性を意識していたようで、それは何よりも主人公の名前・「宗助」にあらわれていますし、あらすじで紹介したように、最後のほうで宗助に参禅させます。
しかし『門』という小説の魅力は、そうした「頭でっかちなテーマ」よりも、むしろ幸福そうに自足しながら、でもどこか陰のあるサラリーマン夫婦の日常を、秋から冬、冬から春という季節の移り変わりにシンクロさせながら淡々と描き出した、その筆致にあるといえます。
そして、そうした「日常のリアリティー」を構築するうえで、漱石は東京という都市空間を巧みに利用しています。次回は、いよいよ、『門』に描かれた神保町界隈の紹介です。
深津