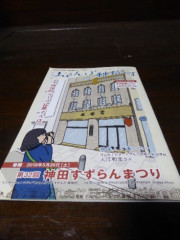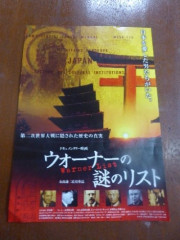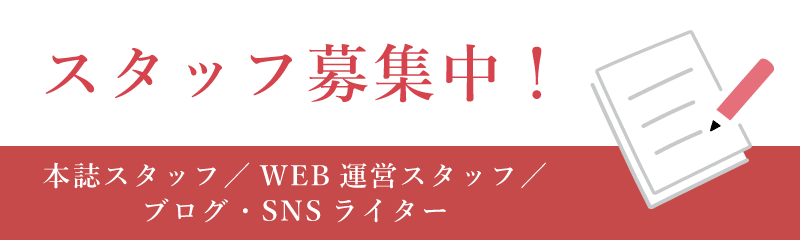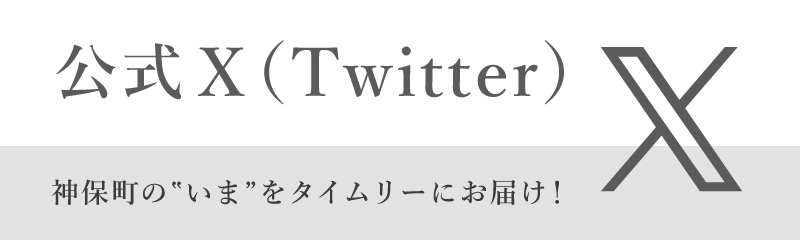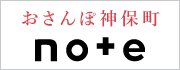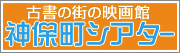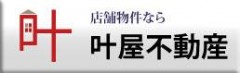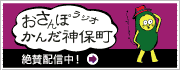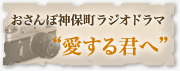2018/04/29 18:18
おさんぽ神保町25号配布
神田すずらん通りの街路樹のマロニエ(紅花とちの木)が紅色の花を咲かしていました。 おさんぽ神保町の春号の印刷があがってくる季節です。 おさんぽ神保町の印刷があがってきたら、地元の商店に配布に行きます。 今日スタッフが集まり、配布しました。 駿河台下から、靖国通り沿いの店舗に設置をお願いして回ります。 配布するおさんぽ神保町25号を見ると 表紙は、神保町女子のOLコハル子さんが写真を撮っているところです。
今回から表紙のイラストの担当者が変わり、イラストの雰囲気が変わりました。今回のイラストもなかなか味があります。 コハル子さんが撮っているのは文房堂さんの建物でした。 文房堂さんの建物は大正11年(1922年)に建てられましたが、大正12年の関東大震災で焼失します。焼失を免れた正面外装部分のみ記念に保存し内部を建替えて現在に至ります。 おさんぽ神保町の中を開くと、第32回すずらんまつりのご案内の 次に、特集の神保町レトロ建築さんぽが掲載されていました。
建築専門の書店(古書ばかりでなく新刊の建築の本も販売しています。)南洋堂書店の関口奈央子さんが解説しています。 学士会館と一誠堂書店の建物が書かれていました。 学士会館の建物は昭和3年(1928年)、一誠堂書店の建物は(昭和6年(1931年)。関東大震災以後、鉄筋コンクリート造の建物として竣工されます。 同じページに、大正14年(1925年)頃竣工された十一軒長屋が、掲載されていました。 明治36年(1903年)の神田古本分布図を見ると、関東大震災前の駿河台下から神保町交差点までの間には古書店はあまりありませんでした。
映画「ウォーナーの謎のリスト」を観に行ったとき、巌松堂に勤めていた藤井正さんが戦時中招集され、宿直で一緒になった本好きの中尉と、神保町の三省堂書店から九段下までの本屋の店名を順に言い出すシーンがあります。 十一軒長屋ができていたこの時代には長屋に多くは書店が入っていたと思われます。 映画では、その後中尉は特攻に行き亡くなりますが、 その数日前、藤井さんを外地に行かないよう上司に取計らい、藤井さんは生き残りました。 おさんぽ神保町の配布に靖国通りを歩き現在2軒のみ残っている長屋の前を通ります。
2軒の長屋に入っていた「本と街の案内所」は、すずらん通りに移転してシャターが閉まっていて、三鈴眼鏡店は休みのためシャターが閉まっていました。
島田 敏樹
2018/03/31 18:26
神田明神奉納プロレス
相撲に奉納相撲があるように、プロレスも奉納プロレスをやってみようと、 神田すずらん祭りや神保町ブックフェスティバルでおなはし会をしたり、地元の劇団の神田時来組でも活躍されているホワイトカレーの神保町チャボの店長の根岸さんが、神田明神の祭務所地下ホールで奉納プロレスを開催しました。 11時にねぎかぉコショタンのお話し会、ちびっこプロレス教室等子ども向けのイベント。 昼にイベント用に館内で売っていた神保町チャボさんのホワイトカレーを食べて、 14時からゴングです。
14時に館内に戻ってみると満席ですごい熱気でした。 第1試合は神田そば打ちレスラー櫻井匠とちびっこプロレス教室校長渡辺宏志の神田プロレス組VSピラミット王 秀・オブ・ザ・イルミティと神田でも番町松崎和彦の悪者レスラー組の対戦です。 レフリーの見ていないところで、秀・オブ・ザ・イルミティさんが椅子を使って反則をしてきたのに対し、低い天井に関わらず、櫻井匠さんのドロップキックの技が決まっていました。
次の試合は神田プロレス選手会長那須晃太郎と神田スポーツ店連絡協議会公認レスラー神田スキーフェラリ―組VS浅草プロレス主催雷神矢口と忍者ファイター茉峲組の対戦です。 那須晃太さんは観客に神田、神田のコールをあおって浅草が地元の雷神矢口さんと対抗していました。 この試合は、神田スキーフェラリ―さんの引退試合で、神田スキーフェラリ―さんは雷神矢口と茉峲組の反則に耐えて、スリーカウントのフォール勝ちします。 試合後神田スキーフェラリ―さんの引退セレモニーで、角谷さんが記念品を渡しました。
本日のメインイベントはCCWカナディアンヘビー級王者藤原秀旺対正則学園野球部出身レスラー佐藤恵一のタイトル戦です。 王者藤原秀旺さんは最初は、紳士的に握手をしてきたものの レフリーの見ていないところで、スーツから凶器を取り出したり、場外どころか館外に飛び出すなどの大乱闘。
佐藤恵一さんは立ち直って、エルボードロップを繰り出して反撃しますが、 最後は、王者藤原秀旺さんのバックドロップで、スリーカウントのホールド負けでした。 迫力満点の試合でした。
島田 敏樹
2018/03/11 18:39
おさんぽ神保町地図校正
フリーペーパ―のおさんぽ神保町の25号の最後のページに載せる地図校正の時期が来ました。 毎回地図に載せる店舗に変動がないか調査するため、街を歩いて、地図を校正するのです。 神保町交差点の岩波ホール前におさんぽ神保町のスタッフが集まり、それぞれ担当する街を歩いて回りました。 私が担当したのは、神田すずらん通りです。 神保町交差点から白山通りを下って行き、 さくら通りの前で、白山通りを渡ります。 地下鉄の入り口から、さぼうるの通りに入り、まっすぐに行くと、定食屋の「ふらいぱん」が閉店していました。
神保町の街の変化は、他の街に比べ緩やかですが、それでも少しずつ変化しています。 ここ数年、神田すずらん通り界隈は、大きく変化しました。 チャーハンの大盛りが桁外れだった町中華の徳萬殿 陽の目を見ない昭和の本に光をあて、蘇らせてお店に並べていたキントト文庫 写真集、コミック、ゲーム雑誌等新刊本が並んでいたすずらん堂
特色のあるお店が、神保町から消えていくのが、胸が痛みます。 昨年、おにぎりの小林が閉店したのはすごく残念でした。 おにぎりの小林は、昔、果物店でした。 その頃、サンドイッチも置いてあり、買いに行きました。 その側には、大きな猫が寝ていて、近づいても逃げませんでした。 それから、しばらくしておにぎりが売られているようになり、すずらんまつりや神保町ブックフェスティバルのボランティアの昼休みの時、毎回たべました。
おにぎりは、短い昼休みに早く食べれて、ワゴンを見て回ることができるので助かります。 三省堂書店の前の神保町シアターに行く道を曲りました。 神保シアターの隣りには、ラーメン二郎が移転してきています。 長い行列が十字路で途切れながら並んでいました。 その先を真直ぐ行き、神保町三井ビルにでます。 神保町三井ビルの噴水の前で、寒桜が咲いていました。
島田 敏樹
2018/03/04 18:45
『おさんぽ神保町』編集長と古書店街ぐるっと巡ろう
おさんぽ神保町の編集長が、ほぼ毎週土曜日に行っている神保町街歩きに参加しました。 朝11時に神保町駅A9の出口 で待ち合わせをして出発しました。 まず、学士会館に行きました。 茶色のスクラッチタイルに覆われたモダンでクラシックな建物。
関東大震災後の昭和3年(1928年)建てられた耐震耐火の鉄筋鉄骨コンクリートの建物です。 それから、白山通りを渡り、さくら通りの山形屋紙店に行きました。 明治12年の創業し、店の裏側には、大正元年に造られ、関東大震災や東京大空襲にも耐え抜いた立派な倉があります。
再び、白山通りを渡り、すずらん通りに入りました。 池波正太郎が上海焼きそばと食べたという揚子江菜館、 その先の小諸そばに入っているビルは震災復興建築です。 その向かい側には、すずらん通りに移った本と街の案内所でした。
本と街の案内所は、膨大の本の在庫を抱える本の街神保町の在庫を本を求めて神保町に訪れる人に図書館のようにどこの書店にあるか検索してもらえる場所です。 新しい本と街の案内所は、さらに神保町の名所についても検索し、オリジナルの地図とその解説をプリントアウトできるようになっていました。
本と街の案内所を出て、先を進むと江戸川乱歩が穴子天丼を食べたはちまきさんがあります。 先に進むと、文房堂のアンティークな建物があり、駿河台下のすずらん通りの入り口から、靖国通りに出ました。 すずらん通りは、まだまだ古い建物が残っているとはいえ、ここ数年でずいぶん変わってしまったなと思います。 靖国通りに行ってしばらく行くと、浮世絵の看板が見えました。
和本の大屋書房がありました。 それから、靖国通りを間直ぐに行き、京都便利堂、神田古書センター、ブッケン・ロック・サイド、矢口書店をえて、ブックハウスカフェに行きます。 神保町に唯一のこどもの本の新刊本の専門店ブックハウス神保町がありました。 昨年2月に惜しまれつつ閉店してしまいます。 ブックハウスカフェの店長さんは、神保町にこどもの本の専門店を残したいという強い思いで、ブックカフェとして,こどもの本専門店を再スターとしたと語っていました。
島田 敏樹
2018/02/12 18:52
新島襄生誕之地碑前祭
2月12日(日)新島襄の誕生日です。神田錦町3丁目に生まれ、後に同志社大学を創立しました。 神田錦町3丁目にある学士会館の前には碑があり、同志社大学は毎年新島襄の誕生日の2月12日に学士会館の碑の前で碑前祭を行っています。 今年も、学士会館の碑の前で、碑前祭を行っていました。
今年のNHKの大河ドラマは「西郷どん」ですが、新島襄は、数年前NHK大河ドラマの「八重の桜」の新島八重の夫です 明治維新後、日本は、開国により、儒教に基づくアジア文化を脱して、個人主義の西洋文明を受け入れていきます。 そんな日本について、新渡戸稲造は米国で問われました。 「西洋には、キリスト教があるが、日本にそれに相当する道徳があるのか。」と それに対して、新渡戸稲造は英文で「武士道」を書きます。 「日本の象徴である桜の花と同じように日本の土に根差した武士道という花がある。それを育てた社会は消滅した。しかし、かつて存在した遠い星々が今も我々を照らし続けているように封建制の子として生まれた武士道は、その母なる社会が死した後も生き残って、今なお我々に道徳の道を照らしている。」 それは、各国に翻訳され、多くの海外の人に読まれました。 10時45分になり、新島襄の碑前祭が始まりました。
まず、讃美歌を歌います。 同志社大学はキリスト教精神でできた大学です。 米国に留学した新島襄も、西洋化に進んで行く日本に、道徳教育の必要性を感じ、キリスト教主義の学校同志社大学の前身同志社英大学を創立しました。 碑前祭で碑の前で、同志社大学の学長がお話しになられていました。
建学の精神の「良心」教育を受け継いでいきますと
島崎 敏樹