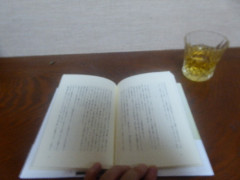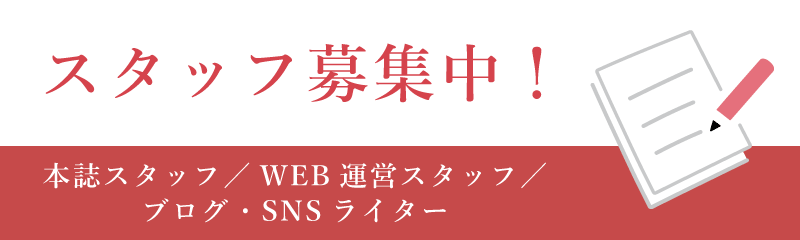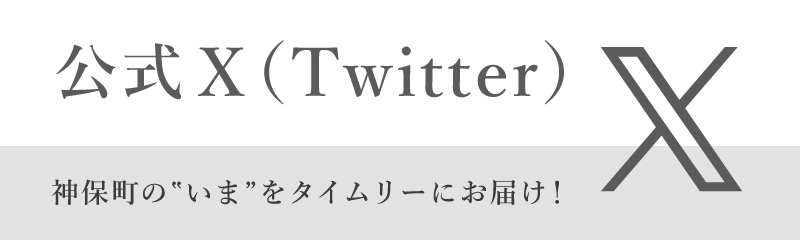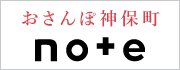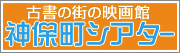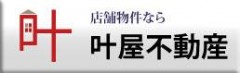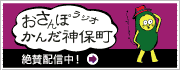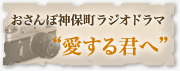2016/01/01 09:28
火花
おさんぽ神保町をWEB版ご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。 昨年中は、おさんぽ神保町のWEB版をご覧になって頂きまして、 ありがとうございました。 今年も神保町の街情報及び関連情報を皆様にお届けしてまいります。 今年も、おさんぽ神保町を宜しくお願い申し上げます。 昨年平成27年度上半期の芥川賞の受賞者は、お笑い芸人コンビ「ピース」の又吉直樹さんの「火花」が選ばれました。 「火花」は、お笑い芸人の世界を描いた小説です。本の帯には、「笑いとは何か、人間が生きるとは何なのか」「日本中を席巻する傑作!」と書いてありました。
お正月に、読んでみようと思い、昨年中に三省堂で買っておきました。 お笑い芸人の有名人が書いた話題作が芥川賞を取ったので、芥川賞の発表以来、発行部数は伸び12月の段階で、245万部に達しています。三省堂でも、「火花」はタワー積みで、置いてありました。 「火花」の著者のピースの又吉直樹さんは、昨年話題となったということで、昨年の大みそかの紅白歌合戦で審査員をやられていました。
ピースの又吉直樹さんは、神保町ともいろいろと関係しています。神保町花月に出演したり、神田古書連盟の神保町公式ガイドVol.2で表紙を飾り、芸人界で最も本の街・神保町を愛する男で、芥川龍之介の「トロッコ」や太宰治の「人間失格」等を愛読する読書家として紹介されていました。 また、2016年度の神保町公式ガイドVol.6でも、「神保町に代わる街はない。やっぱり(神保町は)夢の国です。」と語っていました。 お正月に初詣に行った後、「火花」を読みました。148頁の本なので、直ぐに読み終えてしまいました。 「火花」の物語は花火大会の余興で呼ばれたお笑い芸人が、天才である先輩芸人に弟子入りするところから始まります。
主人公は、世間のタブーに挑戦しても、自分が面白いと思ったことを優先し、全力で挑む先輩芸人を尊敬し、そんな芸人になろうとします。 やがて、主人公は、先輩のような芸人になれないことに気付きます。 世間を完全に無視して、自分が面白いと思ったことだけを優先するお笑いは、誤解を招き誰かを傷つけることになりかねない。 そして、それは人に優しくないことであり、面白くないのと同義だと。 芥川賞受賞作品 「火花」 又吉直樹 著 文藝春秋 は、神保町書店にて発売中です。
島田 敏樹
2015/12/29 09:34
神保町柳屋―年越しそば
大みそかの年越しそばにはまだ早いのですが、蕎麦を食べたくなり、神保町柳屋さんに行きました。神保町柳屋さんは神保町にあるお蕎麦屋さんです。
神田でお蕎麦屋さんと言えば、須田町の神田まつやさんや、淡路町のかんだやぶそばさんが有名ですが、神保町界隈にも、神田錦町更科さん、満留賀静邨さん、専大前満留賀さん、満留賀そば店さん、神保町柳屋さん等のお蕎麦屋さんの老舗名店があります。
神保町柳屋さんは創業100年近くなる老舗のお蕎麦屋さんです。

神保町駅A7の出口から、白山通りを学士会館の方に進み、東京パークタワーの手前で曲ると、ありました。
途中のすずらん通りの入り口には門松が飾られていて、新しい年を迎える準備をしています。
神保町柳屋さんに着くと、東京パークタワーの1階の木の看板に、行燈、黄色い暖簾がかかった風情のあるお店でした。神保町柳屋さんは神保町の再開発により、移転し東京パークタワーの1階にお店があります。

お店の中に入ると、仕事納めの翌日(29日)の2時近くだったためすいていました。おねえさんに「お好きな席に」と言われたので、壁際の席に座りました。メニューを見ると、もり、ざる、ごま汁、とろろ、なめこおろし、かしわ南蛮、カレー南蛮、天ぷらそば等があります。天もりを注文しました。
再開発前、父は神保町柳屋さんに昼毎日のように食べに行き、判で押したようにもりそばを注文していました。
父に連れられて私も、再開発前の神保町柳屋さんに何回か食べに行ったことがあります。当時赤坂へ移転する前の日本で1,2を争う広告代理店博報堂さんの本社の近くに神保町柳屋さんがあり、店内に入るとサラリーマンがひっきりなしに来ていました。お手伝いのおばさんが大勢いましたが、休む間もなく注文を受け蕎麦を運び片づけていました。帳場には、小机を置いた畳の上に着物を着たおばあさんが座っていました。
そんな神保町柳屋さんは平成12年(2000年)再開発によりお店は取り崩されますが、平成15年(2003年)に東京パークタワーの1階で、営業を再開します。

神保町 柳屋さんが移転した後、博報堂さんも赤坂に本社を移転し、本社ビルは平成21年(2009年)に再開発により取り崩されます。本社ビルは、昭和5年(1930年)竣工しニコライ堂を再建した岡田信一郎氏が設計した街のランドマークとなる建物だったため、平成27年5月15日に、テラススクエアの1部として、再建されました。
暫くして、おねえさんが、蕎麦を持ってきてくれました。天婦羅は、パリッとしています。
歯ごたえのある蕎麦を濃い汁に少しつけて食べました。再開発で移転しても変わらない味です。
蕎麦を食べ終わり、蕎麦湯を飲みおわり、お会計にレジに行ったとき、お店のおねえさんに聞くとお店の営業は今日(29日)まですが、大みそかの31日に11時30分~14時までの間、お持ち帰り用の蕎麦を販売する とのことです。
島田 敏樹
2015/12/24 09:36
クリスマスキャロルの夕べ
夕方駿河台下から、靖国通りを神保町交差点に向かって歩いていると、神保町交差点に人ごみができていました。行ってみると、毎年クリスマスの時期が近づくと共立女子校生により行われる神保町交差点でのクリスマスコンサートでした。
神保町交差点は、靖国通りと白山通りを交差していて、都電の時代には両通りを走る都電の路線を乗換える神保町駅があり、また地下鉄の時代になってからは都営三田線、新宿線、半蔵門線の3線が乗り入れる神保町駅の出入口ができ、岩波ホールが建てられました。

そのため、神保町の中心として、1959年(昭和34年)から、始まった秋の神田古本まつりの会場に毎年なり、春のさくら祭りでは甘酒がくばられ、クリスマスが近づくとコンサートを行う等のイベントの会場となります。
白山通り沿いはクリスマスのイルミネーションの飾りつけがなされていました。神保町交差点もイルミネーションを設置してあり、イルミネーションの隣でクリスマスコンサートを行っています。
行って見ると、すごい人で、歩道の半分が埋め尽くされ、おさんぽ神保町の知り合いが、お手伝いで交通整理をしていました。
人ごみの中から中を覗くと、共立女子校の中高生が、サンタの帽子を被って、クリスマスソングを演奏しています。

共立女子校は、1886年(明治19年)に創立され、1938年(昭和13年)に建てられ、その施設のゴシック調のモダンな建物の共立講堂が有名です。共立講堂は、現在学内行事のみに使用されていますが、日比谷公会堂と並ぶ大規模な講堂のため、日本レコード大賞、コンサート等に使用されていました。

クリスマスコンサートは夕方の5時から、共立女子中高生の吹奏楽部の演奏が始まり、5時半にスパークリングワインとホットチョコレートが配られ、6時から共立女子中高生音楽部の演奏が始まるそうです。
島田 敏樹
2015/12/22 09:38
カリー専門店エチオピア本店
食事を取らないまま夜の10時近くなってしまったので、胃にもたれないエチオピアのカレーを食べて帰ろうと、エチオピア本店に行きました。
アフリカのエチオピアは、コーヒー発祥の地です。コーヒーは、エチオピアからイスラム教徒に飲まれ、ヨーロッパに伝わり、大航海時代で全世界に広まりました。
カレー店のエチオピアは、昭和63年創業時には、インド風カレーとコーヒーの店だったことから、このコーヒー発祥の地の名前がつけられました。

エチオピア本店は三井神保町ビルを通って駿河台下に行き、駿河台下の交差点を渡って、御茶ノ水駅に向かって明大通りを歩いて行くとあります。
三井神保町ビルは、クリスマスのイルミネーションが、綺麗に飾り付けられていました。
エチオピアに着くと並ばずに店内に入れました。エチオピアは行列のできる人気カレー店ですが、さすがにこの時間は行列ができていません。それでも、店内にはまばらに人がいました。
店内に入ると券売機が有りました。券売機に書いてあるメニューは、チキン、ビーフ、野菜、豆などのカレーとドリンク、サラダ等があります。野菜と豆のカレーとコーヒーの食券を買いました。

カウンターの席に座ると、ウエーターさんが水とジャガイモをもってきてくれました。ジャガイモは、おかわり自由だそうです。食券を渡すと、カレーの辛さを聞かれました。カレーの辛さのレベルは、0~30まであります。辛さの0で、中辛レベルだそうです。とりあえず、辛さは3にしました。
しばらくして、ウエーターさんが、カレーを持ってきてくれました。
カレーには、レタス、ブロッコリー、ナスと豆等が入っています。
辛さ3では、多少辛さを感じましが、辛すぎるというものではありませんでした。
香辛料の味と、レタスや豆、ナス等とよくあいます。
カレーを食べ終わった後にコーヒーをもって、来てくれました。

アフリカのエチオピアコーヒー豆は、イエメンのモカ港から輸出していたことから、モカと言われています。カレー店のエチオピアも、カレーには、モカが合うと、創業時からしばらく自家焙煎で、モカコーヒーをネルでドリップしていました。
コーヒーを飲むとカレーにあう酸味のある味がします。
食事が終わり外にでると。もう夜の10時を過ぎていたので、ラストオーダーの時間が過ぎ、外のお店の電気は消されていました。

島田 敏樹
2015/12/16 09:41
山の上ホテル-水出しコーヒー
先日読んだ神保町ファンタジー「幻想古書店で珈琲を」で主人公の古書店のアルバイトの司が、店主の魔法使いの亜門と山の上ホテルで、水出しコーヒーを美味しそうに飲む場面がありました。水山しコーヒーを飲みに行きたくなり、山の上ホテルに行ってみることにしました。
山の上ホテルは、駿河台下から明大通りに出て、明治大学のリバティータワーと大学会館の間の吉郎坂を上って行くとありました。1937年(昭和12年)に建築されたアール・デコ調のクラシカルな西洋洋館です。
山の上ホテルは、出版社の多い本の街神保町に近いことから、締切が迫った作家が小説を書きあげるためにカンヅメにされたホテルです。カンヅメになっても、居心地のいいホテルなので、川端康成さん、松本清張さん、吉行淳之介さん、三島由紀夫さん、山口瞳さん、池波正太郎さんなどの文人たちが、宿泊していました。
山の上ホテルの中には、宿泊施設やウエディングのためのチャペルの他に、英国風カウンターバーノンノン、ダイニングのラビィ、中華料理の北京、鉄板焼きガーデン、選りすぐりのワインが飲めるモンカーヴ、天婦羅と和食の山の上、コーヒーパーラーのヒルトップ等のレストランやバーがあります。
水出しコーヒーはコーヒーパーラーヒルトップで飲めます。ヒルトップは山の上ホテルの入り口から入り、正面を右に曲り、階段を下りていくとありました。

お店の中に入ると、白い壁に池波正太郎さんの絵が飾ってあり、居心地がいい店内です。ウエイターさんに「お好きな席を」と言われたので、窓際の席に座りました。窓の外は錦華坂です。机に立てかけてあるメニューを見ると、ランチに牡蠣フライセット、牡蠣グラタンセット、牡蠣のパッパルデッテがあり、またセットメニューに小海老のマカロニグラタンや、ビーフカレー等から選ぶAセットとBセットがありました。
デザートには、特製デザートアップルパイや悪魔の食べ物等があります。リンゴの美味しい季節なので、アップルパイも美味しそうでしたが、「幻想古書店で珈琲を」で亜門と司が食べていたチョコレートケーキはこの悪魔の食べ物だろうと思い、ストロングコーヒー(水出し珈琲のホット)と悪魔の食べ物を注文しました。

水出しコーヒーは、コーヒーの抽出をお湯ではなく、水を用いるコーヒーです。水を用いるため専用のガラス器具を使い12時間かけて抽出します。
加熱しないため珈琲豆の苦みの成分が溶けにくく、あまりコーヒーに抽出されずマイルドな味になります。
暫くして、ウエートレスの人が、ストロングコーヒーと悪魔の食べ物を持ってきてくれました。
悪魔の食べ物は、チョコレートケーキにクリ―ムが添えてあり、ケーキの外側がパリッとしていました。亜門と司が食べていたチョコレートケーキのようです。
亜門と司は、ウインナーコーヒーを注文していましたが、ストロングコーヒーも悪魔の食べ物によくあいました。
ケーキを食べ終わり、コーヒーを飲み終わって、勘定を済ませて、裏口から外に出ました。帰りは錦華坂を下りて帰りました。

錦華坂を下りていくと右下には、美術学院に通っていたころの松任谷由美さんのお気に入りの場所で、「白い朝まで」で歌われた錦華公園があります。
錦華公園の紅葉や銀杏の葉は赤や黄色に染まっていました。
島田 敏樹