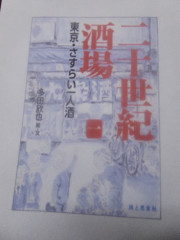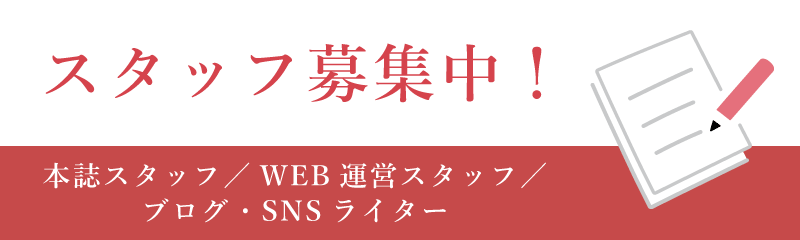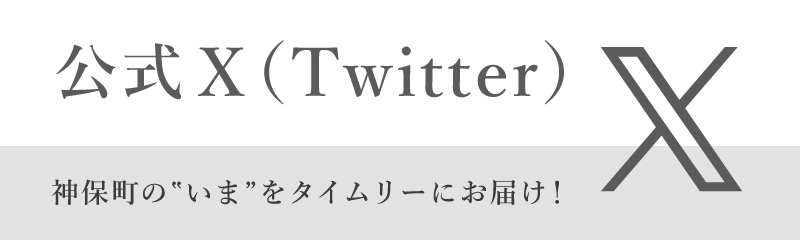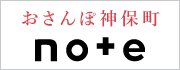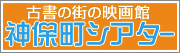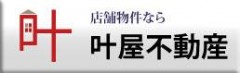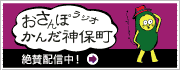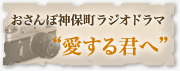2015/11/27 09:56
大衆酒場飲み歩き入門講座のご案内
大衆酒場飲み歩き入門講座のご案内
多田欣也の大衆酒場入門(1)
「二十世紀酒場(一) 東京・さすらい一人酒」は、10月より旅と思索社から発売された著者の多田欣也さんが二十年の歳月をかけてめぐった、消えゆく、変わりゆく昭和の古き良き酒場でのささやかな一杯の思い出を手書き絵と文章で記した、飲み歩きイラストエッセイです。
本書の発売を記念して、大衆酒場めぐりを楽しみたいと思っている方々のための入門講座を開催します!
講師はもちろん、著者の多田欣也氏。
そして、ナビゲーターはフリーアナウンサーの田中くるみさん。自らも初心者として大衆酒場の楽しみ方を学びます。
「二十世紀酒場(一)」の概要は下記リンクから!
http://tabistory.jp/publish/9784908309014_nijusseikisakaba01/
「多田欣也の大衆酒場入門」概要
◆場所:「@ワンダー/ブックカフェ二十世紀」様
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-5-4 開拓社ビル2F
http://jimbo20seiki.wix.com/jimbocho20c
◆日時:2015年12月3日(木)19時から21時を予定。
◆定員:30名様 空きがあれば当日参加も可能です。
◆参加費用:ワンドリンク+ワンスナック(カクウチの雰囲気を味わえる乾きもの)でお一人様1,800円。追加オーダーも可能です。
◆内容
●著者自己紹介
大衆酒場で飲み始めた時期やきっかけ、著者の酒場めぐりのスタイルのほか、イラストを描くきっかけや書籍刊行のきっかけなどをご紹介します。
●酒場めぐり入門講座
一人酒を楽しむテクニックをはじめ、必ず頼みたいメニュー、常連さんと仲良くなるコツ、マナーやエチケットなど、素朴な疑問から楽しみ方までを伝授します。
●著者おすすめの酒場紹介
場所、佇まい、料理、お客さんなどなど、著者が印象に残った名店の数々をご紹介します。また、初心者でも訪問しやすい都内の酒場、いつかは行ってみてほしい上級者向けの酒場などもご紹介します。
●著者との情報交換タイム
今さら聞けない酒場の常識をはじめ、酒場情報やぜひ聞いてみたいこと、どしどしご質問ください!
当日は本の販売も行います。また講座終了後に、ご希望の方には著者による本のサイン(持ち込み本も可)、記念撮影会を行います。
旅と思索社 について
2014年5月、東京・神田錦町で産声を上げた、一人出版社「旅と思索社」です。
「コアな旅」がテーマの旅のストーリーWebマガジン「Tabistory.jp」、「二十世紀酒場(一)」をはじめとする書籍の刊行を行っています。
http://www.tabitoshisaku.co.jp/
http://tabistory.jp/
参加申し込み方法は下記よりご確認ください。
http://tabistory.jp/cat_news_publication/2819/
島田 敏樹
2015/11/23 09:58
ロスジェネの逆襲
先々月、三省堂に行ったら、1階の文庫本の新刊本コーナーでタワー積となっている文庫本を見つけました。見ると2013年に最高視聴率を獲得し、決めセリフの「倍返し」が流行語大賞に選ばれたテレビドラマ「半沢直樹」の原作「オレたちバブル入行組」「オレたち花のバブル組」の続編「ロスジェネの逆襲」の文庫本の新刊が出たのです。(現在タワー積は「下町ロケット」にとって代わられています。)
バブル期の1988年に夢を抱いて銀行に入行した半沢直樹が、中間管理職としてバブル崩壊の後始末に追われるお話しの続編です。単行本の時に買って読んでなかったので、1冊買って読んでみました。

ロスジェネ世代とは、バブル崩壊後の失われた10年(1994年~2004年)の間に世の中に出た若者のことを言います。
バブルを挟んで、団塊の世代、バブル世代、ロスジェネ世代と呼ばれる世代に分けられていました。
団塊の世代は、高度成長期やバブル期の成功体験を基に事業の拡張や投資を行い、借金や融資を膨らませます。
バブル世代は、バブル崩壊後、団塊世代の事業拡張や投資のため負った巨額の借金の返済や不良債権処理に追われました。
ロスジェネ世代は、バブル崩壊の親の失敗を見て育ったので、事業拡張や投資には慎重にならざるを得なくなります。

そして、大きな組織の中で、上司である団塊世代のやり方が、間違っていると思っても受け入れてしまうバブル世代がいる中で、半沢直樹は、戦っていきました。
テレビドラマでは、融資を急がせ、そのお金を妻に転貸させた香川照之さんの演じる大和田常務の不正を半沢直樹が取締役会で暴き、土下座させます。
そのロケ地となったのが、学士会館の2階でした。
学士会館は、旧帝大7大学の同窓会として、建てられた会館です。神保町A9の出口から出ると、道の向こう側に昭和3年(1928年)に建てられたレトロな茶色の建物が見えます。そこが、学士会館です。
学士会館2階のロケ地は、半沢直樹放送時に、土下座の間と呼ばれてました。

「ロスジェネの逆襲」では、ライブドアの日本放送の買収事件を思わせるIT企業の買収のお話しです。
子会社に出向させられた半沢直樹がロスジェネ世代の森山とともに、IT企業買収案件を横取りした東京中央銀行と戦います。
就職氷河時代のロスジェネ世代の森山は、初めはバブル世代の半沢に反発します。バブル世代は好景気だったというだけで、多量に採用され、上司の言うことをたとえ間違っていても聞いていれば組織に守られる。そのしわ寄せは自分たちにくるのだと
そんな森山を半沢は諭します。「戦え、後10年もすれば、君たちの時代は来る、戦って組織を変えてみろ、正しいことを正しいと言えず、ひたむきに誠実に働いた者が報われない社会はおかしいのだと」。
「ロスジェネの逆襲」
池井戸 潤 著 文春文庫
神保町の書店に販売しています。
島田 敏樹
2009/09/08 10:10
田山花袋『東京の三十年』(その2)
1886(明治19)年、上京した花袋(録弥)の一家は「牛込の奥」に落ち着きます。今で言うと、都営新宿線・曙橋駅あたりになるでしょうか。当時のその周辺の様子を、花袋は『東京の三十年』の中で次のように書いています。引用は岩波文庫版に拠ります。
*
その時分には、段々開けて行くと言ってもまだ山手はさびしい野山で、林があり、森があり、ある邸宅の中に人知れず埋れた池があったりして、牛込の奥には、狐や狸などが夜ごとに出て来た。(「再び東京へ」)
*
以上が、120年近く前の曙橋駅周辺の様子。今では地下鉄が通っているのですから、不思議なものです。それはさておき、上京した花袋は、文学雑誌に投稿する傍ら、友人と文学談義をしたり、英語学校に通ったりしながら、貪欲に新知識を吸収します。その主な舞台が、神保町を中心とする神田一帯でした。たとえば花袋は、当時大学予備門(東大の前身)の学生だった野島金八郎に感化をうけるのですが、二人は「東京の市街を其処此処と言わずほうつき歩」きながら、文学談義に耽ります(たしかに、散歩の最中には、よいアイディアが浮かんだりします)。以下、その部分の記述です。
*
神田橋のゴタゴタした下宿屋の並んだ汚い空気、元、学習院のあった錦町から護持院原の傍を掠めて一つ橋通に出て行く路、鎌倉河岸から今川橋の方へ行く通などをも私たちはよく歩いた。小川町の角にあった三角堂という小さな店では、かれはよくインキやペンや鉛筆などを買った。そこは肥った豊かな頬をした娘がいた。(「再び東京へ」)
*
彼らの散歩コースが、神田一帯に集中しているのは、野島が通う大学予備門が、今の如水会館から共立女子大学一帯にあったことと無関係ではないでしょう(ちなみに、大学予備門の跡地に入ったのが東京商業学校(一橋大学の前身)で、一橋の名称はこれに由来します)。
また、当時花袋が通っていた英語学校は仲猿楽町(今の神保町二丁目周辺)にありました。つまり、「牛込の奥」から仲猿楽町まで、今の地下鉄の駅でいうと3駅分。そこを花袋は歩いて往復していたことになります。その時の様子を、『東京の三十年』では次のように記しています。(引用文中の/は改行を表します)
*
その時分は、大通りに馬車鉄道があるばかりで、交通が不便であったため、私たちは東京市中は何処でもてくてく歩かなければならなかった。牛込の監獄署の裏から士官学校の前を通って、市谷見附へ出て、九段の招魂社の中へぬけて神田の方へ出て行く路は、私は毎日のように通った。今日と比べて、人通りは多く、馬車が絡繹として、九段坂の上などは殊に賑やかな光景を呈していた。/大村の銅像、その頃はまだあの支那から鹵獲(ろかく)した雌雄の獅子などはなかった。丁度招魂社の前のあの大きな鉄製の華表(とりい)が立つ時分で、それが馬鹿げて大きく社の前に転がされてあるのを私は見た。そしてそれが始めて立てられた時には、私は弟と一緒に、往きに帰りに、頬をそれに当てて見た。夏のことなのでその鉄の冷たいのが気持が好かった。私と私の弟とは一緒に神田にある英語の学校に通った。/九段の坂の中ほどの左側に今でも沢山鳥のいる鳥屋の舗(みせ)がある。それがその頃にもあって、私と弟とはよく其処に立っては、種々(いろいろ)な鳥をめずらしそうにして眺めた。インコ、鸚鵡、カナリア、九官鳥、そういう鳥のいる籠に朝日が当って、中年の爺がせっせっと餌を店の前で擂鉢ですっていた。目白、ひわなどもいれば、雲雀、郭公などもいた。(「明治二十年頃」)
*
文中最初のほうにある「牛込の監獄署」というのは、今の新宿区富久町あたりにあった東京監獄・市谷刑務所のこと(のちの「大逆事件」(1910(明治43)年)で幸徳秋水らが処刑された場所です)。「士官学校」の跡地には、戦後、防衛庁が入りました。『ノルウェイの森』の回にもふれましたが、1970年11月25日、三島由紀夫はここで割腹自殺します。また、「招魂社(しょうこんしゃ)」は靖国神社のことで、すでに1879(明治12)年には、東京招魂社から靖国神社に改称されていましたが、一般には、招魂社の名で親しまれていたそうです。
次回は、花袋が野島と散歩した一ツ橋界隈と、通学路として毎日のように通った靖国神社界隈の“今”を、当時と比較してみます。
深津
2009/04/03 10:05
田山花袋『東京の三十年』(その3)
ここしばらくの間、「デジカメの不調→パソコンの故障」とトラブル続きで、だいぶ更新を滞らせてしまいました。すみません。引き続きぼちぼち更新を続けていきますので、今後ともよろしくお願いします。
さて、田山花袋『東京の三十年』の続きです。しばらくぶりなので、前回までの話を簡単にさらっておきましょう。1886(明19)年、田舎から上京した「花袋」少年は、文学で身を立てようと、東京で新知識の吸収に励みます。その主な舞台が、神田から九段にかけての一帯でした。『東京の三十年』には、この頃の神田・九段界隈の様子がよく描かれています。
たとえば、花袋は当時、仲猿楽町(今の神保町二丁目周辺)にあった英語学校に通うため、自宅のある「牛込の奥」から毎日、今の靖国通りを往復しています。「文学散歩」らしく、私たちも「花袋」少年が歩いた道をたどってみましょう。本文は前回も引用しましたが、「その頃」と「今」とを対照するために、必要なところはもういちど引用していきます。
まず、神保町から靖国通りを九段に向かって歩いて行きましょう。1927(昭2)年竣工の名建築・九段下ビルを右に見て、日本橋川に架かる俎橋を渡ると、そこはもう九段「下」。文字どおり坂「下」にあり、目の前には九段坂が伸びています。
九段坂は、明治の中頃までは、今よりももっと急坂で、坂の上からは浅草辺まで見通すことができたそうです。また、比較的なだらかな坂になったあとも、坂下には、大八車の後押しをして日銭を稼ぐ「立ちん坊」と呼ばれる労働者がたくさんいて、この界隈には、彼らをあてこんだ木賃宿や飯屋が多くあったといいます。たとえば、国木田独歩の「窮死」(1907(明40)年)という短編小説は、今でいう「ワーキンプ・プア」、あるいは「ホームレス」の人々の実態を描き出した佳作ですが、その冒頭は、「九段坂の最寄にけちなめし屋がある」という一文から始まります。ちなみに独歩は、花袋の盟友といわれる短編小説の名手で、有名な「武蔵野」のほかに、「運命論者」「正直者」なども面白いです。この機会にぜひご一読ください。
さて、九段坂を途中まで上ってうしろを振り返ってみます。下の写真は、坂の中腹から「浅草」方面を望んだ「今」の様子。俎橋(高速道路の下に架かってます)あたりまで見通すのがやっとです。
写真の左側には、今では、「北の丸スクエア」や「東京理科大」の大きな建物が並んでいますが、『東京の三十年』によれば、明治の頃、このあたりには鳥屋の舗(みせ)があったようです。
*
九段の坂の中ほどの左側に今でも沢山鳥のいる鳥屋の舗(みせ)がある。それがその頃にもあって、私と弟とはよく其処に立っては、種々(いろいろ)な鳥をめずらしそうにして眺めた。インコ、鸚鵡、カナリア、九官鳥、そういう鳥のいる籠に朝日が当って、中年の爺がせっせっと餌を店の前で擂鉢ですっていた。目白、ひわなどもいれば、雲雀、郭公などもいた。(「明治二十年頃」)
*
上でいう鳥屋とは、今でいうペットショップみたいなものでしょう。江戸期から明治期にかけて、町人たちの間で鳥を飼うことが風流な趣味として流行っていたようで、たとえば、谷崎潤一郎『春琴抄』のなかにも、女主人公・春琴の「小鳥道楽」の様子が描かれています。
話を戻して再び坂を上ります。坂を上りきったところの大きな鳥居が靖国神社。『東京の三十年』では、次のように描かれています。
*
大村の銅像、その頃はまだあの支那から鹵獲(ろかく)した雌雄の獅子などはなかった。丁度招魂社の前のあの大きな鉄製の華表(とりい)が立つ時分で、それが馬鹿げて大きく社の前に転がされてあるのを私は見た。そしてそれが始めて立てられた時には、私は弟と一緒に、往きに帰りに、頬をそれに当てて見た。夏のことなのでその鉄の冷たいのが気持が好かった。
*
引用文の1行目にある「鹵獲(ろかく)」とは「戦利品として分捕る」という意味。大鳥居の周辺に鎮座するこの獅子は、1895(明28)年、日清戦争に際して日本軍が中国の遼東半島から運んできたものだといいます。また、「大村の銅像」というのは、もちろん、今も参道にそびえる大村益次郎像のことです。大村益次郎(1824-69)は近代兵制の樹立者で、銅像は1893(明26)年に建てられました。ちなみにこの像は、戊辰戦争(1868-69)の際、明治政府に敵対した彰義隊が立て籠る上野の山の方角を、いまも睨みつけています。
(写真は靖国神社境内の唐獅子と大村像です。大村像は上野の山を睨んでいます)
上の写真は第二鳥居。夏の暑い日、「花袋」少年が頬を当ててその冷たさを楽しんだ鳥居は、入り口の大鳥居でなく、こちらの第二鳥居です。1887(明20)年竣工。本文には「鉄製」とありますが、正確には「青銅製」。青銅製としては日本最大の鳥居だそうです。
靖国神社周辺はいまがちょうどお花見シーズン。『東京の三十年』を片手に、120年前の靖国神社周辺に思いを馳せてみるのも楽しいのではないでしょうか。次回は、九段坂を下って日本橋川沿いに「花袋」少年の足跡を訪ねます。
深津
2009/02/03 10:11
田山花袋『東京の三十年』(その1)
今回取り上げるテキストは『東京の三十年』(岩波文庫)。田山花袋(たやま・かたい)の自伝的エッセイです。
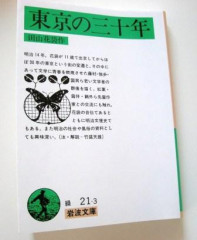
花袋は、今では、これまでここで取り上げた漱石や村上春樹にくらべ地味な作家かもしれません。しかし、日本の近代文学史にとっては、非常に重要な作家のひとりです。「実物」を手にとったことはないけれど、文学史の試験勉強で覚え(させられ)た、代表作「蒲団(ふとん)」の名前だけは記憶にある、という方も案外多いのではないでしょうか。
田山花袋(本名:録弥)は1872(明治4)年、現在の群馬県館林市生まれ。没落士族の出身で、16歳の時、就職した兄を頼って一家で上京。困窮の中、文学の道を志します。このあたりは帝国大学出のエリートだった鷗外や漱石と大きく違うところです。(じつは録弥は10歳の時、丁稚奉公として東京に出されるのですが、不始末を仕出かして田舎に帰されています)。
なんとか文壇に食い込んだ花袋は、当初は感傷的な美文作家として知られますが、いっぽうで、当時最新流行の外国文学を積極的に摂取。これが「描写」という技法に結実し、日本の近代文学は実質的にここから始まります。 "明治30年代"末のことです。
ちなみに「描写」というのは、ココロ(目に見えないもの)を風景や表情・動作など目に見えるものに置き換えて間接的に表現する描法です。たとえば、今の小説(ライトノベル)なら、「クリスマスなのに、彼女(彼氏)がいなくて淋しい」とベタにココロのありようを表現するのでしょうが、これが「描写」文体だと、「彼(彼女)は、幸せそうに寄り添うカップルから目をそむけながら、イルミネーションの街を足早に通り過ぎた。彼(彼女)の頬を冷たい風が打った。」......という感じになります。文学史的には、まず、後者の文体が創出されてから、そののちに、前者のような文体が定着していくのですが、文学の専門的なハナシになるのでここで止めます。
いずれにせよ、"明治40年代"の花袋は文壇の強力なリーダーのひとりであり、『蒲団』、『田舎教師』といった代表作もこの時期発表されます。この頃はちょうど漱石の活躍時期――『三四郎』『それから』『門』の前期三部作の頃です――とも重なっており、今でこそ、漱石が日本文学の本流という印象がありますが、この時期にかぎっていえば、花袋が本流、漱石は傍流という見方が当時の文壇の一般的な見方だった、というのも面白いところです。
さて、『東京の三十年』です。このエッセイは、1917(大正6)年に刊行された自伝的エッセイで、修業時代の思い出が東京の街の変遷に重ねあわされる形で回想されています。次回はこの中から神保町界隈に関わる記述を拾い出してみましょう。
深津