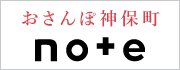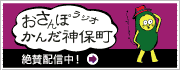2009/02/03 10:11
田山花袋『東京の三十年』(その1)
今回取り上げるテキストは『東京の三十年』(岩波文庫)。田山花袋(たやま・かたい)の自伝的エッセイです。

花袋は、今では、これまでここで取り上げた漱石や村上春樹にくらべ地味な作家かもしれません。しかし、日本の近代文学史にとっては、非常に重要な作家のひとりです。「実物」を手にとったことはないけれど、文学史の試験勉強で覚え(させられ)た、代表作「蒲団(ふとん)」の名前だけは記憶にある、という方も案外多いのではないでしょうか。
田山花袋(本名:録弥)は1872(明治4)年、現在の群馬県館林市生まれ。没落士族の出身で、16歳の時、就職した兄を頼って一家で上京。困窮の中、文学の道を志します。このあたりは帝国大学出のエリートだった鷗外や漱石と大きく違うところです。(じつは録弥は10歳の時、丁稚奉公として東京に出されるのですが、不始末を仕出かして田舎に帰されています)。
なんとか文壇に食い込んだ花袋は、当初は感傷的な美文作家として知られますが、いっぽうで、当時最新流行の外国文学を積極的に摂取。これが「描写」という技法に結実し、日本の近代文学は実質的にここから始まります。 "明治30年代"末のことです。
ちなみに「描写」というのは、ココロ(目に見えないもの)を風景や表情・動作など目に見えるものに置き換えて間接的に表現する描法です。たとえば、今の小説(ライトノベル)なら、「クリスマスなのに、彼女(彼氏)がいなくて淋しい」とベタにココロのありようを表現するのでしょうが、これが「描写」文体だと、「彼(彼女)は、幸せそうに寄り添うカップルから目をそむけながら、イルミネーションの街を足早に通り過ぎた。彼(彼女)の頬を冷たい風が打った。」......という感じになります。文学史的には、まず、後者の文体が創出されてから、そののちに、前者のような文体が定着していくのですが、文学の専門的なハナシになるのでここで止めます。
いずれにせよ、"明治40年代"の花袋は文壇の強力なリーダーのひとりであり、『蒲団』、『田舎教師』といった代表作もこの時期発表されます。この頃はちょうど漱石の活躍時期――『三四郎』『それから』『門』の前期三部作の頃です――とも重なっており、今でこそ、漱石が日本文学の本流という印象がありますが、この時期にかぎっていえば、花袋が本流、漱石は傍流という見方が当時の文壇の一般的な見方だった、というのも面白いところです。
さて、『東京の三十年』です。このエッセイは、1917(大正6)年に刊行された自伝的エッセイで、修業時代の思い出が東京の街の変遷に重ねあわされる形で回想されています。次回はこの中から神保町界隈に関わる記述を拾い出してみましょう。
深津