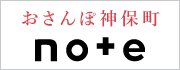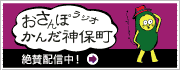2008/12/19 10:14
村上春樹『ノルウェイの森』(その3)
だいぶ更新が滞ってしまいました(すみません)。前回の続きです。
『ノルウェイの森』では、「僕」と直子が東京をぐるっと半周する散歩コースの中に、神保町が描き込まれていました。以下、2回に分けて、この場面の重要性について考えます。
まず、この場面の「僕」の直子の位置関係を確認しておきましょう。前回の引用文で、二人は連れ立って歩いていますが、並んで歩いてはいません。「僕」は、「直子の一メートルほどうしろを、彼女の背中とまっすぐな黒い髪を見ながら歩い」ているのです。
この微妙な距離感の理由はいろいろ考えられます。たとえば、「僕」にとって直子は、何よりもまず、自殺した親友(キズキ)の恋人でした。「僕」と直子の関係は、キズキを介して成立していたわけで、直接的な繋がりではありません。再会したのも1年ぶりです。だから、ある種の遠慮が働いているのではないか、とふつうは考えるでしょう。
しかしこの小説の中で、二人の間の距離感はもう少し別の、より重要な意味を担っています。たとえば、東京をぐるっと歩き回る(だけの)二人の奇妙なデート(?)は、このあとも、日曜日ごとに繰り返されます。「僕」はなぜ、自殺した親友の恋人と会い続けるのでしょうか。「僕」にもその理由が分かりません。分らないまま、毎日曜日には、直子のうしろを歩き続けるわけです。もっとも、季節の進行とともにその距離は徐々に縮まっていきます。夏休みが終わる頃には、「僕」は直子と並んで歩くようになります。しかし、二人の間のちょっとした距離感は解消しません。たとえば、冬の寒い日。互いにしがみつくようにして散歩する場面でも、「僕」には、二人の間に介在するダッフルコートの布地一枚ぶんの(僅かな)距離が感得されます。「僕」にとって直子は、一メートルであれ、コートの布地一枚ぶんであれ、つねに、ちょっとした隔たりの先に感得される存在なのです。そして比喩的に言うなら、「僕」は日曜日毎に、ちょっとした隔たりの先に感得される直子を追いかけるように、東京中をぐるぐる回ります。
こうした「僕」の行為は、直子の心的状況を、身体的に反復しているようにも読めます。東京で再会した直子は、うまく言葉が出てこないという、精神的危機を抱えていました。その状態を、彼女は次のような比喩で語ります。第二章からの引用です。
*
「うまくしゃべることができないの」と直子は言った。「ここのところずっとそういうのがつづいているのよ。何か言おうとしても、いつも見当ちがいな言葉しか浮かんでこないの。見当ちがいだったり、あるいは全く逆だったりね。それでそれを訂正しようとすると、もっと余計に混乱して見当ちがいになっちゃうし、そうすると最初に自分が何を言おうとしていたかがわからなくなっちゃうの。まるで自分の体がふたつに分かれていてね、追いかけっこをしているみたいなそんな感じなの。まん中にすごく太い柱が建っていてね、そこのまわりをぐるぐるとまわりながら追いかけっこしているのよ。ちゃんとした言葉っていうのはいつももう一人の私が抱えていて、こっちの私は絶対にそれに追いつけないの」
*
このように、直子の危機は、「ちゃんとした言葉」を抱える「もう一人」の自分――ほんのちょっとの先に感じられる「正しい」自分――を追いかけた、ぐるぐる回りの状態として把握されます。では、直子はなぜ、こうした危機に陥っているのでしょうか。テキストはその答えを明示しませんが、キズキの死が、そのきっかけであることが仄めかされます。
いっぽう、「僕」もまた、キズキの死以降、「ちゃんとした言葉」を欠いた状態にあります。「僕」にとって、キズキの死がいかに「重かった」かは、第二章の次の記述から窺えます。
*
(キズキが死んでから――深津注)僕はまわりの世界の中に自分の位置をはっきりと定めることができなかった。僕はある女の子と仲良くなって彼女と寝たが、結局半年ももたなかった。彼女は僕に対して何ひとつとして訴えかけてこなかったのだ。僕はたいして勉強をしなくても入れそうな東京の私立大学を選んで受験し、とくに何の感興もなく入学した。
*
ふつうに考えれば、「僕」はかなり独善的で、ひどい奴です(笑)。でも、ここでは話を先に進めます。東京の大学に入ってからの「僕」の生活は、たとえばこんなふうに記されます。第三章からの引用です。
*
大学の授業でクローデルを読み、ラシーヌを読み、エイゼンシュタインを読んだが、それらの本は僕に殆んど何も訴えてこなかった。僕は大学のクラスでは一人も友だちを作らなかったし、寮でのつきあいも通りいっぺんのものだった。寮の連中はいつも一人で本を読んでいるので僕が作家になりたがっているんだと思いこんでいるようだったが、僕はべつに作家になんてなりたいとは思わなかった。何にもなりたいと思わなかった。
*
東京で出てきても、あいかわらずひどい状態ですが(笑)、ここで確認しておきたいのは、キズキの死後、「僕」が言葉というものに対して、正面から関わっていないということです。それは本来なら、「僕」にとって、相当深刻な精神的危機であるはずです。にもかかわらず「僕」は、直子がそうであるようには、自らの危機をはっきり自覚していません。しかし、「『正しい』自分を追いかける直子」を追いかけるという行為のうちに、危機からの回復を図る「僕」の無意識が読み取れます。「僕」にとって直子は、「僕」の危機以前、つまりキズキが生きていた頃の「正しさ」に繋がる唯一の手掛かりだからです。
長くなってきたので、ここまでの議論を整理します。『ノルウェイの森』の(人間)関係のプロトタイプは、ちょっとした隔たり=距離感です。その根本には、キズキの自殺があります。キズキの自殺をきっかけにして、直子は「正しい」自分から疎外され、その結果、「正しい」自分をぐるぐる追いまわし、「僕」もまた、その直子を追いかける形で「正しさ」を追い求めるのです。
このときに、追及する「正しさ」が、今の自分にとってあまりにかけ離れた存在だったら、そもそもそれを追いかけようとしないでしょう。「正しさ」は、手を伸ばせばすぐ近くにある(ように感じられる)。だからこそ、それを追いかけるのです。この意味で、東京を散歩する「僕」と直子の間の微妙な距離感というのは大事です。こうした関係はまた、この物語を回想する37歳の「僕」と、20歳で死んでしまった直子の関係にも当てはまります。
このような、小説内の関係のプロトタイプが、神保町が登場する『ノルウェイの森』の一節によく表れているのですが、ここでは、地名も重要な意味を持ちます。次回はこの点について考えていきます。
深津