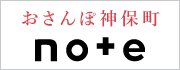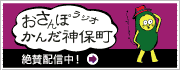2009/01/28 10:13
村上春樹『ノルウェイの森』(その5)
またしばらく更新が滞ってしまいました。お許しください。『ノルウェイの森』は今回で最後です。
さて、『ノルウェイの森』の中でも、学生運動について触れられています。そして、表面的に見れば、「僕」は学生運動に対しかなり冷淡です。たとえば、第四章には次のような一節があります。
*
ストが解除され機動隊の占領下で講義が再開されると、いちばん最初に出席してきたのはストを指導した立場にある連中だった。彼らは何事もなかったように教室に出てきて、ノートをとり、名前を呼ばれると返事をした。これはどうも変な話だった。何故ならスト決議はまだ有効だったし、誰もスト終結を宣言していなかったからだ。(略)僕は彼らのところに行って、どうしてストをつづけないで講義に出てくるのか、と訊いてみた。彼らには答えられなかった。答えられるわけがないのだ。彼らは出席不足で単位を落とすのが怖いのだ。(略)僕はしばらくのあいだ講義には出ても出席をとるときには返事をしないことにした。
背の高い学生がビラを配っているあいだ、丸顔の学生が壇上に立って演説をした。ビラにはあのあらゆる事象を単純化する独特の簡潔な書体で「欺瞞的総長選挙を粉砕し」「あらたなる全学ストへと全力を結集し」「日帝=産学共同路線に鉄槌を加える」と書いてあった。説は立派だったし、内容にとくに異論はなかったが、文章に説得力がなかった。信頼性もなければ、人の心を駆りたてる力もなかった。(略)この連中の真の敵は国家権力ではなく想像力の欠如だろうと僕は思った。
*
ここで興味深いのは、「僕」がみせる妙なこだわりです。「僕」は、言行不一致の学生活動家を責め、彼らへのあてつけとして、出席を取られる際返事をしません。学生活動家に対する「僕」の批判は正論ですが、しかし前述したように、キズキの死以降、「僕」の言葉も彼らに負けず劣らず空疎でした。学生活動家を批判する「僕」は、この点に気づきません。いや、むしろそれを否認したいから、学生活動家の言行不一致に対し、必要以上に過敏な反応を示すのかもしれません。過剰な反応の背後には、必ず、何かを(強調することで)隠したい、否認したいという気持ちが働きます。この場合、「僕」が否認しようとしているのは、「僕」と学生活動家(学生運動)が実は同質の危機を抱えている、という現実です。いわば、根っこの部分を共有しているのです。
ところで、この小説は、37歳の「僕」の回想形式になっている、という話をいちばん最初にしました。ここに賭けられているのは、37歳の「僕」の自己救済です。そのために「僕」は、1970年の直子の死を描く必要がありました。直子の死を契機に、20歳の「僕」が(危機から)救われたからなのですが、この仕組みについて説明すると長くなるので省きます(興味がある方は、私が以前書いた『ノルウェイの森』論をご覧ください。『ジェンダーで読む 愛・性・家族』(東京堂出版)という本に収められています。なんだか宣伝めいて恐縮ですが)。
ただ、ここで確認しておきたいのは、37歳の「僕」の自己救済をかけた回想が、(敗北した)学生運動の記憶が固着した場所を、直子と直子(=正しさ)を追いかける、つまり正しさから疎外された僕を歩き回らせる場面からはじめられているという点です。それはまるで、何かを確認する「儀式」のようですらあります。
そういえば、『ノルウェイの森』のエピグラフには、「多くの祭の(フエト)ために」とあります。ここでいう「祭(フエト)」が何を意味するのか、テキストには何も書かれていません。しかし、「祭(フエト)」、「日常からの解放」、「狂騒」という連想で、これが1970年前後の若者の政治反乱(=「敗北した」学生運動)を指している気がしてなりません。だとすると、『ノルウェイの森』のエピグラフは、80年代後半の「今」から、70年前後の「祭(フエト)」を悼んだものであるようにも読めます。そして、この「悼む」という行為が、神保町界隈を含む神田・本郷辺を歩く「僕」と直子の身振りに集約的に象徴されているように感じるのです。
冒頭にも記したように、『ノルウェイの森』という小説は、バブル期の日本ではオシャレな恋愛小説として受容されました。しかしこの小説に底流しているのは、やはり、「祭(フエト)のあと」という主題です。じっさい韓国や中国では、若者の政治反乱(フエト)が終わったあと、この小説が熱狂的に支持されたといいます。じつはそのほうが、この小説の本質をついているのかもしれせん。
昨年、『実録連合赤軍』(製作・監督 若松孝二)という映画を見に行った時、本編上演前に流されていた「神田解放区(神田カルチェラタン)闘争」のニュースフィルムを見て驚きました。靖国通り(古書店街)で、学生と機動隊の「市街戦」が行われているのです。今ではまったく想像できませんが、これもまた、本の街、そして学生の街・神保町に刻まれた歴史のひとコマです。私が大学生だった頃(20年前ほど前)は、それでも、たとえば明治大学の記念館と「立て看板」は健在で、「往時の」雰囲気が多少は残っていました。けれども、現在のお洒落な(?)キャンパスからは、70年前後の記憶を想起するよすがもありません。
『ノルウェイの森』が描きだす東京は、一見したところ、(この小説が出版された)1980年代後半が舞台であるかと錯覚するほどクールで、そしてお洒落です。しかしよく読むと、周到に隠された「僕」のトラウマとその時代――70年前後の風景が浮かび上がってくるはずです。そこから、フエトの頃の神田神保町界隈に思いを巡らしてみてはいかがでしょうか。
深津